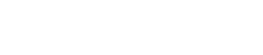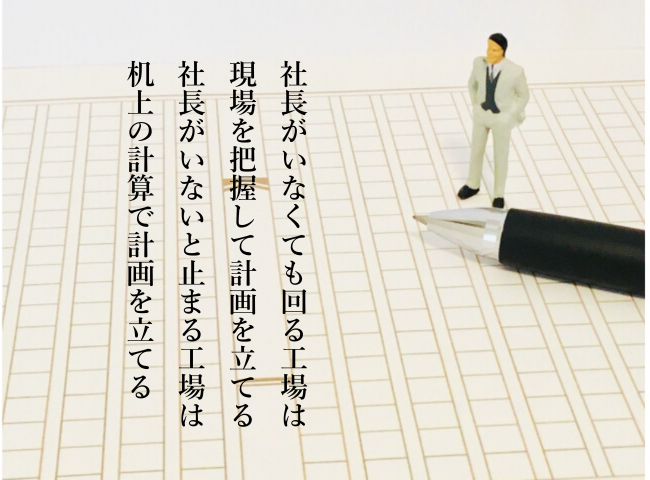
久しぶりに金属加工工場のA社長と話をする機会がありました。
この方とは、よく「管理者の育成」の話が出てくるのですが、今回は、今月いちばん忙しく、そのときの管理者の仕事ぶりで困っているようでした。
月末が近づいてくると、受注状況がまとまってきて翌月の生産計画を立てることになります。
その受注数は今年度で一番多く、社内のだれもが「来月は忙しくなるぞ・・・」と思っているところでした。
その生産計画を立てるのは、アラフィフ世代のB課長です。
受注情報の他に、設備能力、作業者の対応能力、資材の在庫状況や入荷状況、完成品の在庫状況、有給取得する社員の把握等、様々な情報を集め考慮し、納期に間に合うよう生産スケジュールを作成します。
これまでの実績がありますので、計算しなくともおおよその計画は頭の中でできています。
そして生産スケジュールを立てるために構築したシステムで細かいところまで決定していきます。
いつものように、立てた計画を全作業者に発信し、それを受け作業者も個々の作業に向かいました。
しかし月の中頃、A社長は気になります。
今月は、今年度で一番多い計画数なのに、月の中頃にすでに計画の7割近くが終わっている。
前月に比べ、何か特別に生産能力が上がるような何かを導入したわけではありません。社員が増えたわけでもなく、勤務体制が変わったわけでもありません。
その月は、ちょうどタイミングよく、A社長と全社員との面談の月でした。
社員一人一人といろいろな話をする中で、多くの社員がなんだか疲弊しているような感じを受けたそうです。
そこで勤怠状況を確認してみると、先月より時間外勤務が明らかに多い。残業申請も出ておらず、社長も把握できていなかったのだとか。一体現場で何が起こっているのだろうと疑問に思いました。
【B課長という人物】
B課長は、いわゆる就職氷河期世代です。
製造業だけでなく、どの業界も「就職氷河期世代」の人たちで構成されていることが多いのではないでしょうか。年齢的にそのような地位に就く人が多くなります。
高校生、大学生時代はバブルの絶頂期。自分もその恩恵を受けるべく、良い企業に就職して活躍しようと思っていたところにバブルがはじけ、一気に就職先がなくなったのです。就職活動をして何十社から内定をもらうつもりでいたところが、急に何十社も面接受けても内定ももらえないという状況になり、その中でなんとか掴んだ就職先。
サービス残業は当たり前、有給休暇も取ったこともない、ミスをすれば「他にも代わりはいるよ」などと言われながらも、努力してきた人物でした。その努力は人間性にも表れています。
そんな苦しい時代を乗り越え、ようやく自分が管理職になり、自分が思い描く会社、部署にしようとした時、今度は学生、若者の売り手市場。
指示命令をすればすぐにパワハラと言われ、若者優先で有給休暇は消化され、若者ができなかった部分は自分がフォローし、有給休暇は泣く泣く諦めざるを得ず・・・。
そんな状況の中でB課長は、
「自分はこれだけやってきた。今の若者は”ぬるい”」
「自分がこれだけやっているんだから、みんなもやれるはずだ」・・・。
こんな思考になっている上司は、実はとても多いのではないでしょうか。そして、その「当たり前」が、現場とのズレを生んでいることに気づいていない。
【計画の落とし穴】
B課長は、翌月の生産計画を立てます。
受注情報、設備能力、在庫状況、社員の有給取得予定など、様々な情報を把握し、システムを駆使して細かいところまで計画を立てていました。
そしてこの月は、後半に有給取得者が多いことを把握し、月の前半に7割近く終わらせる必要があると判断し、計算上も問題ないと判断し、全社員に発信したのでした。
これまで社長をやってきて、ここまで情報を把握し、システムを使いこなす社員はいませんでしたので、社長は安心して任せていました。
そして、これまでうまくコントロールしてきたB課長です。今年度で一番計画数が多い月でもなんとかしてくれるだろうと安心していました。
しかし、なかなか思うようにはいかなかったようです。
確かに計算上はできるのでしょう。それでも計画通りにならないことが当たり前の生産現場です。少しでも設備にトラブルが発生すればB課長の計画は崩れます。
その対応策が、全社員に普段以上の残業を強いるものだったのです。
「ここまでやってから終わってくれる?」と、数時間の残業直後の残業指示や、「ここまで追い上げるから明日も残業できるよね」と翌日の残業指示。
社員も受注情報から「今月は忙しくなるぞ」とは思ってはいたものの、想像以上に残業依頼が続いたのです。
社員は、「今月は仕方がない」と思いながら残業依頼は受けるも、さすがに残業の依頼のされ方が急すぎて、まったく自分の意思を言える状況にもありませんでした。
そんな状況が続いたため、社長との面談では疲労感が伝わってきたのでしょう。
しかし、B課長からすれば、
「昔はこれくらい当たり前だったから。この一か月くらいいいっしょ。」
「自分が経験してきたことに比べれば、このくらいなんともないよね」
それくらいの程度にしか考えていないようでした。
【社長がやるべきこと】
B課長は、悪気があったわけではありません。むしろ、優秀で責任感も強く、仕事を100%完了させる努力を怠りません。
しかし、彼のあたりまえが、今の社員のあたりまえではなかったのです。
生産計画を立てるだけなら、数字をかき集めてくれば可能です。設備の能力、材料の必要数、在庫数などから計算すれば(計算できれば)、だれでもほぼ同じ答えを出すことができます。
しかしこれでは情報が足りないのです。
それは、計画を実行するのはだれか?という部分が欠落しているから起こります。
計画を実行するのは社員です。計画通りに動こうとしますが、人間ですからその通りにならないこともあります。設備も計算通りに動けばいいですが、何かしらトラブルが起こるのが普通と考えてもいいのが工場です。
これまでの実績から、それを考慮したとしても、トラブルから復帰させるのは社員です。社員ごとに能力も違えば気分も違います。同じ社員でも調子のよいときもあれば悪いときもあります。
今回立てた計画は、それがすべて良いということが前提で立てられた計画だったために、少しでもなにかがあれば、残業でカバーするしかなかったのです。
社長の管理監督責任だと言われればそれまでですが、なにもかも社長のせいにされても困ります。原因を明確にして対処しなければいけません。
B課長の仕事は、生産計画を立てそれを完了させることが最大の仕事でしょう。
しかし、その計画が、ただ数字上の計算をしただけで、社員の状況や都合、様子も何も考慮することなく実行したのでは、当月はなんとかなったとしても、それが来月も、半年後も同じことが続くのかと思った社員は、あっという間に気持ちが切れてしまいます。
それは、就職氷河期を経験してきたかどうかに関係なく、だれにでも起こり得ることです。これをB課長は考えなければいけません。
外から聞いていれば当たり前のことではありますが、その当事者になったときには得てしてそのような行動になってしまうものです。
このようなことは社長から伝える必要があるでしょう。
その忠告だけでは、これからは気を付けてね、という話で終わってしまいます。構造的には何も変わっておらず、また次に同じことをしてしまうかもしれません。
A社長はどうすればよかったのでしょうか。
B課長に計画の立て方を指示する、指導するというのは間違いです。
課長が把握していない情報があれば、社長から情報提供すべきです。また、情報を収集できる環境構築がとても重要です。
数字だけでは見えない、現場の負担感。そのようなことも管理者が把握できるような仕組みがあるかどうか。このような情報提供ができる社長は、工場を社員に任せられるようになるでしょう。
そして、任せられれば、工場が自動稼ぎ装置に近づいていきます。