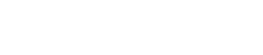47.工場経営における本質的な優先順位 ーーー社員のためにやるべきこと
.png)
突然ですが、私は今月1歳(推定)になる2匹の保護猫を飼っています。
工場経営のコラムに何の関係があるのか?と思われるかもしれませんが、本質的なつながりを感じたのでここに書いておこうと思います。
中途半端な経験のやり直し
15年ほど前、野良猫が我が家に突然やってきました。家の周りを走り回ったり、網戸によじ登ったり、ちょっと迷惑だなあと感じながらも、ケンカ盛りの息子、娘たちが、猫との出会いをきっかけに突然ケンカがなくなり、これは猫に感謝しなければ、としばらく飼うことにしたのです。
しかし、家の中に入れる勇気はなく、家の外に寝る場所を作り、餌をやって外猫のまま飼うことにしました。
それから約1年半が経ったとき、2,3日帰って来ませんでした。心配していると突然帰ってきて、「おかえりー!」と思ったのですが、こちらの目をじっと見て「にゃー」と鳴いて去っていったのです。突然の別れでした。
直後はモヤモヤしながらも、猫は外で自由な方がいいのかと自分を納得させていました。
しかし、いろいろ調べてみると、どうやら外猫の世界、現実は厳しいようでした。
外猫の寿命は約4年、家猫の寿命は15~20年とのこと。
そして生まれたばかりの子猫が保健所に連れて来られてしまう現実などを知りました。中途半端に猫を飼ったという後悔が蘇り、次はちゃんと最期まで飼おうと思い、ある保護猫団体から、3か月の子猫を2匹引き取ったのです。
猫は高いところが好き、という情報は聞いていましたが、事実、人間の私には考えもつかない場所に想像もつかないルートで、とても真似できない動きで登って行き、平然とした顔で上からの眺めを楽しんでいます。
一方でそのルート上は物が散乱するのは当たり前。何かが壊れたり破れたり、いろいろなことをあきらめなければいけません。その片付けなどで大変なこともありますが、それでもそれ以上に猫のその行動に感心し癒されますので、差し引きはプラスです。
しかしこのままでは、猫も危険だし、人間の生活も脅かされる。
そこで、DIYを始めました。
「声を聴く」より「環境を観察する」
正直DIYは得意ではありませんが、子猫のためならやるしかありません。
壁に穴をあけ、板を取り付け、天井近くまで登れるようにしました。
天井近くには、安心して過ごせるような場所も作りました。
取り付ける前は、使ってくれるかどうかとても心配になります。壁に傷を付けただけの無駄な苦労になるのが不安なのですが、使ってくれるととても安心します。
そうかと思えば、その場所を取り合いケンカが始まります。仕方なく別の場所にも同じものを作り別々にそれぞれの居場所ができるようにと思い設置すると、次は新しいものの取り合いでケンカ・・・。
こんな繰り返しをしている時に、これは工場で自分がやっていることではないか?と思ったのです。
よく経営では「人が大事」と言われます。そして、社長が社員の声をよく聞くこと、社員に声をかけること、寄り添うことが大事だと言われます。それには私も賛成します。しかし、それ以上に社長がやるべき重要なことがあるのではないかと思うのです。
私と猫の関係を、社長と社員の関係と重ねると、私はもっと猫の声を聴く必要があるのかもしれません。もっと猫のそばにいたり、猫に話しかけたりというようなことをすべきなのかもしれません。
しかし私は、猫の過ごす環境づくりを優先しました。
猫と一緒に居れば、鳴き声や表情でおなかが空いたのか遊んでほしいのか、それくらいのことはわかりますが、実際のところ餌をあげれば大抵おとなしくなりますので、ホントのところは猫の話を聞いても何もわかりません。
それより、猫が快適そうにしているか、環境の結果猫がどのように過ごしているのか、という観察の方がとても重要だと思ったのです。
外猫の寿命が短いのは、明らかに家の中より環境が厳しいからです。そのせいか、外猫の目つきは家猫のそれとは明らかに違います。とても厳しい、険しい目をしています。
たとえ家の中で飼ったとしても、ボロボロのケージに閉じ込めたり、トイレを汚いまま放置すれば、それは外よりも厳しい環境かもしれません。飼い主が一日中猫のそばにいても、過ごす環境を良くしてあげなければ、猫は快適になることはありません。
「声をかける」より「環境を改善する」
工場も同じではないでしょうか。
社長が頻繁に現場に出て、社員と対話する、社員の声を聴く、社員と向き合う、そういうことを最優先にしていながら、働く環境作りを疎かにしていれば、社員はどう思うでしょうか。
「あんなにやったのに何も変わらない」「こんな環境で要求ばかりされてもできるはずがない」
「改善して工数削減したのに給与は上がらない」「機械の能力はないのに時間内に生産が終わるわけがない」・・・このような関係性になってしまうのです。
社長は、現場に出るのであれば、環境構築を行った結果、そこで働いている社員がどのように過ごしているのかがとても大事です。
社長が現場に出れば社員が安心すると思ったら大間違いです。それより、壊れたエアコン何とかしてくれ、設備能力を上げる必要があるならそれだけの投資をしてほしい、というのが本当の社員の声でしょう。
私が提唱している「工場の自動稼ぎ装置化」はまさにこの考え方です。
社長が現場に居なければ回らないというのは、社員が社長に言われなければ動かない、自ら考えて動く社員がいないということが原因ではありません。社員だけで生産ができる環境が作られていないのです。
社員が眉間にしわを寄せたり、うつろな目をして頑張っている状況を見て、社長はどんな手を打つでしょうか?
社員に「声をかける」「寄り添う」「向きあう」それも必要なことではありますが、それより先に、社員が働きやすい環境を作ることが必要なのです。
猫のためにDIYが必要なわけではありません。猫が高い場所で過ごすため、安心して過ごすスペースを作るにはDIYが有効な手段だったのです。
工場経営で、評価制度を整えれば社員がやる気を出すかといえばそうではありません。やる気を出してもらうには正当な評価が必要なので、評価制度が都合がいいということです。
IT化をすれば生産性が向上するということではありません。社員がやるよりもITに任せた方がよい作業があるということです。ITに任せればよいことを社員にやらせる環境に問題があるのです。
あなたの工場は、社員が働きやすい環境ですか?
社員に「向き合い」「寄り添った」といえる環境が構築できていますか?