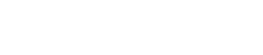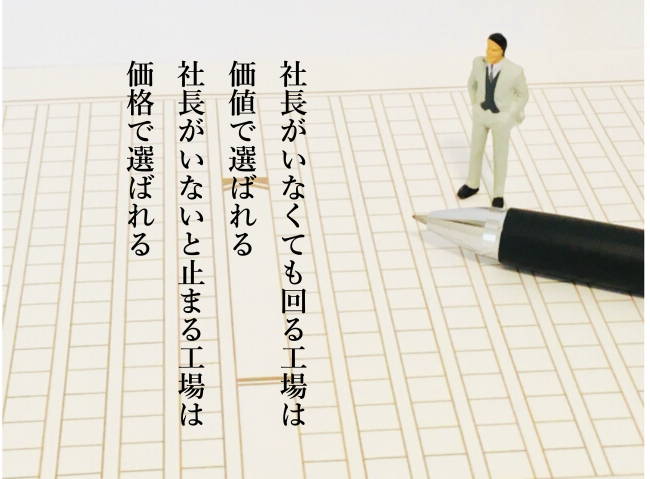
46.価格競争に負けない工場の作り方
ある外食チェーン店で
最近は、大人より子どもの方が忙しいですね。
朝早く学校に行ったと思ったら、帰りは晩ごはんが大人よりも遅い時間になり、家には寝るためだけにしかいないような状態です。
見ていてホントに大変そうに見えますが、本人はやりたいことをやっているようなので、全く文句はないようです。
そんな時間のない子どもと、ある日曜日、久しぶりにショッピングに出かけました。
子どもが学校で必要なものの買い物のため、大き目なショッピングモールに行きました。
昔のようにおさがりでよいっていうことにはなりません。趣味も好みも全く違えば、いちから買いなおすことが始まります。
あれも必要、これも必要、これでいいじゃない?でも1度買ったらもう買うものでもないし買い替えはしたくないし・・・と言っているうちに、クレジットカードの決済額がどんどん上がっていきます。
午後からの買い物がいつの間にか外は真っ暗になり、いつもの晩ごはんの時刻もとっくに過ぎています。
自分のものではないものの買い物は、異様に疲れますね。さらに大きな出費です。久しぶりに子どもと出かけたのでなにかおいしいものでも食べれるお店に行ってみようか、という気にはならず、その辺でさっと食べて帰ろうということになりました。
寄ったのは、全国どこにでもある外食チェーン店。
駐車場から中の様子を見たところ空席はありそうです。何を食べようかと考えながら店内に入ったのですが、席に着くまでに少し違った空気を感じました。
小さな子供がスマホが使いたいと母親に泣きつく声。外の現場仕事の帰りでしょうか、汚れた服のまま食事をしている若者。かかってきた電話に周りの目も気にせず大きな声でしゃべるおじさん。そして、ボソボソと商品名を暗唱してテーブルに食事を置く暗い店員。
回転が速いお店ですので、あっという間にお客さんは入れ替わり、店内の雰囲気も落ち着いて安心して食事をすることはできました。
価格と環境の相関関係
一緒に食事をした家族も同じようなことを感じていたようで、「まあ、チェーン店だし、いろんな客がいるよね」とその状況を共有したのでした。
帰りの運転で「値段なりの環境になるんだな」と思い、同時に「もしかして、こんなところに来る自分たちも、それなりなのか?」という不安にもなりました。
そんな私たちがどのような客だったのかは棚に上げて考えてみると、安い店には、安いなりの理由がある、店員さんによるサービスや店内の環境が、その程度でも構わない客層の来店とスタッフの雇用につながり、その結果がサービスの質やモチベーションなど、すべてが「値段なり」ということにつながってしまっているのではないでしょうか。
これは別に悪いことではありません。食べに行くたびにドレスコードが決まっているようなお店に行くような人ばかりではありません。また、そのような人でもたまには気楽に食べたいときもあるでしょう。それぞれに、その時々に応じて求められたニーズに応えているのです。
しかし、価格を下げれば、何かを犠牲にせざるを得ないのが現実です。
数百円で晩ごはんを食べようと思えば、それなりの量とそれなりの質、それなりのサービスしか受けられません。
最低賃金付近で雇われたアルバイトは、「最低限この程度の仕事をしていればいい」と考えるようになるか、あるいは本当にサービスを提供する能力のない人材しか集まらなくなります。
サービスの提供もそれなり、商品も安さが売り、そうであれば会社の収益性もそれなりになるでしょう。
1店舗ごとの収益が低ければ、多店舗展開をして少ない利益×店舗数にして収益性を上げるしかないのです。
「安く受ける」を続けた先にあるもの
ここまで考えると、この状況、工場経営と同じじゃないかと気付きます。
外食チェーン店でなぜ商品を安く売っているのかといえば、たくさんのお客さんに来てもらうためです。
工場で言えば、仕事量を確保するために「安く受ける」ということと同じ意味です。
利益が少なければ、
- 品質管理に手が回らなくなる
- 設備投資できない、清掃も後回しとなり、職場環境が荒れる
- 良い人材が、育たない、辞めていく、来ない
- 取引先も「安いだけ」を求める客になる
このように、良いサービスが提供できなくなります。
飲食店で最低限の味と量が提供できていればよいと考えれば、工場では図面寸法に入ったものが納品されていればよい、という割り切った仕事になるでしょう。
価格を下げれば、できないことがたくさん出てきます。
それを理解せず、社員に「あれもやれ、これもやれ」と求めているばかりでは、社員からすれば「やってられない」となるのは当然です。
現実を見据えた経営判断
もちろん、経営者だって好きで安く受けているわけではありません。
人件費の上昇、材料費の高騰、エネルギーコストの増加もある中で「適正価格で仕事を受けたい」と思っても、断れば仕事がなくなる不安、取引先からの値下げ圧力があり、思うようにいかないのが現実です。
そして、利益が少なくても社員の生活を守るために、安くても仕方なく受けている仕事もあるでしょう。
しかし、このまま価格競争、自社の安売りを続ければどうなるでしょうか。それが、外食チェーン店の店内のような状況があらわしています。
優秀な人材は採用できず、取引先は安さだけで仕事を出し、その結果職場環境は荒れ、社員も会社は疲弊していく。
このような状況を憂いていても何の解決にもなりません。
小規模工場なら、社長の一存で一気に舵を切れる、経営の自由度が高いことは非常に有利なことです。
価格ではなく、価値で選ばれる工場、「高くても、あなたに頼みたい」と言われる工場への転換は社長の一存で決められます。どのような取り組み内容でかじを切るかも自由です。
簡単ではありませんが、その道は必ずあります。それは、経営者の決断一つです。
価格競争から抜け出し、価値で選ばれる工場になりませんか?