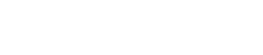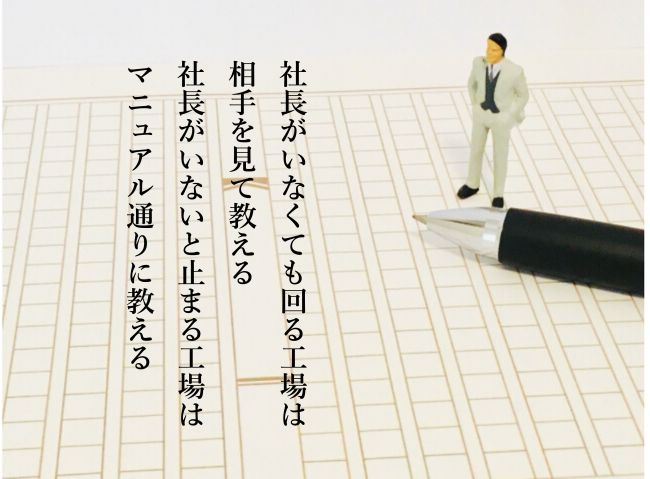
東京のコンビニで見た、無駄のない接客
久しぶりに東京に行く機会がありました。いつも通り飛行機を降り、電車に乗り換え目的の駅まで移動します。何度か東京には来たことあるのですが、いつ来てもなかなか移動時間が把握できません。電車に乗っているといつの間にか1時間軽く過ぎていて、喉がカラカラになっていることがしばしばです。
その駅を降り、改札を出てすぐ目の前に見えたコンビニに入りました。
まっすぐ水のペットボトルを目掛けて店内を歩き、レジ待ちしている間にグミを手に取り、レジの外国人さんに渡します。
あっという間にバーコードを読み取り、支払いのためスマホを出せば、いつ見たのかわからない動作で私の決済方法を見破り、私に確認することもなくバーコードリーダーをスマホにかざし、「ありがとうございましたー。またお越しくださいー。」と日本人と変わらない、いやそれ以上にコンビニ店員としての立派な発音を耳にしてお別れをします。
こちらの方が、彼の流れに身を任せていたら、いつの間にか店の外に出ていたと思うような、流れるような買い物が完了するのです。
地元のコンビニで感じた「丁寧すぎる」違和感
一方、地元のコンビニに立ち寄ったときのことです。レジには、定年退職後と思われるベテランの方がおられました。
「いらっしゃいませ」と丁寧な挨拶から始まり、商品を丁寧に手に取り、確実にバーコードリーダーをかざします。「ポイントカードはお持ちですか?」「レジ袋はご利用になられますか?」「お箸はおつけしますか?」と、一つひとつ確認してくださいます。
もちろん、接客としては何も間違っていません。むしろ、丁寧で親切です。
しかし、正直に言えば、少し面倒に感じてしまったのです。
「ポイントカードは持ってないから大丈夫です」「レジ袋もいりません」と、毎回答えるこのやりとり。急いでいるときは特に、「もうわかってるから、サクッと終わらせてほしい」と思ってしまうのです。
店員さんが悪いわけではありません。ただ、私が求めているものが「丁寧な接客」ではなく、「早く買い物を済ませること」だった、ただそれだけのことです。
東京の外国人店員さんと、地元のベテラン店員さん。
どちらも真面目に仕事をしています。どちらも間違ったことはしていません。
では、なぜ私は東京の店員さんには満足し、地元の店員さんには「面倒だな」と感じてしまったのでしょうか?
それは、私が求めているものを見極めていたかどうかの違いです。
東京の店員さんは、私の様子を伺いながらも手を止めず、全ての作業をやってしまいます。そして、仕事内容を完全に覚え迷いなく作業しています。これは紛れもなく、お客さんの前に出る前にきちんと教育を受け、練習をし、お客さんの前に出る時には体が勝手に動くくらい作業を身につけ、準備してきたということです。
一方、地元の店員さんは、マニュアル通りに「丁寧に」を実践されています。しかし、私が何を求めているのかを見極める余裕がないのか、あるいは「丁寧にすることが正しい」と信じているのか、すべてのお客さんに同じ対応をされているように見えました。
工場のOJTにも同じことが起きている
コンビニを出て、そんなことを考えていたら、ふと先日会った工場の社長の話を思い出しました。その社長はとても社員教育に力を入れておられ、OJTについてもしっかりマニュアルを整備し、誰もが同じように作業できるよう余念がありませんでした。とにかく社員を大事にすることを第一に、とても熱い社長です。
しかし、その話を聞きながら、私は少し違和感を覚えていたのです。
「丁寧に教えること」が、本当に若手社員のためになっているのだろうか、と。
若手社員はまだ多くの仕事ができるわけではありません。教えてもらいながらも給料をもらっている立場です。普通の社員なら、教えられた作業を早く身につけて、自分も早くもらっている給料なりの役に立ちたいと思っているものです。
一方で、ベテラン社員は自分の仕事もあるから時間がないといって、なかなか教えてくれません。ようやく時間が取れたと思ったら、今度は「丁寧に教えなきゃ」「パワハラと思われたらいけない」という意識が先に立ち、必要以上に懇切丁寧に、ゆっくりと説明を始めるのです。
若手社員は内心、「もうわかってますから、次に進んでください」と思っているかもしれません。
ベテラン社員はその様子に気づかず、「ちゃんと理解してもらわなきゃ」と、さらに丁寧に、わかってもらえそうな言葉を探しては説明の仕方を変えて指導を続けます。
その結果、若手社員は「この人の教え方、長いな...それ何回も聞いたよ」「結局何言ってるかわかんねーよ」と思いながらも、ベテラン社員に気を使いながら聞いてあげていたりするものです。
まるで、地元のコンビニで私が感じた「面倒くささ」と同じことが、工場の現場でも起きているのではないでしょうか。
必要な「丁寧さ」とは?
もちろん、OJTが適当でいいという話ではありません。東京のコンビニ店員さんが雑な仕事をしているわけではないのと同じです。
あの店員さんは、ただサクッとやっているわけではありません。お客さんの様子を伺いながらも手を止めず、全ての作業をやっています。そして、仕事内容を完全に覚え迷いなく作業しています。
つまり、お客さんが求めているものだけを、完璧に提供しているのです。
店員さんのこの部分を理解しない人がこの作業を見ると、ただ雑な作業にしか見えないのでしょう。
OJTも同じです。
若手社員が今、何を知りたいのか。何に困っているのか。どこまで理解しているのか。
それを見極めずに、教える側が「丁寧に教えなきゃ」という自分基準で動いていると、若手社員にとっては「面倒くさいOJT」になってしまうのです。また教える側も無駄な時間を割かなければいけなくなります。
大手企業であれば、マニュアル通りに、誰に対しても同じように教えるしかないでしょう。
しかし、全員の顔がわかるような小規模工場であれば、一人ひとりの若手社員の様子を見ながら、その人に合わせた教え方ができるはずです。
「この人はもう理解しているから、次に進もう」 「この人はまだ不安そうだから、もう一度やってもらおう」
そうやって、相手が求めているものを見極めながら教えることができるのが、小規模工場の強みではないでしょうか。
現在のOJTの仕組みが、全てを丁寧に時間をかけて教えなければいけないものになっていませんか?そうだとしたら、習う側、教えられる側どちらも得をしないだけでなく、いつまでも人が育たない工場になってしまっているかもしれません。
ベテラン社員がOJTする時間がないと言い訳しませんか?
若手社員が今、何を求めているか、見極められていますか?