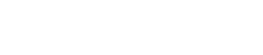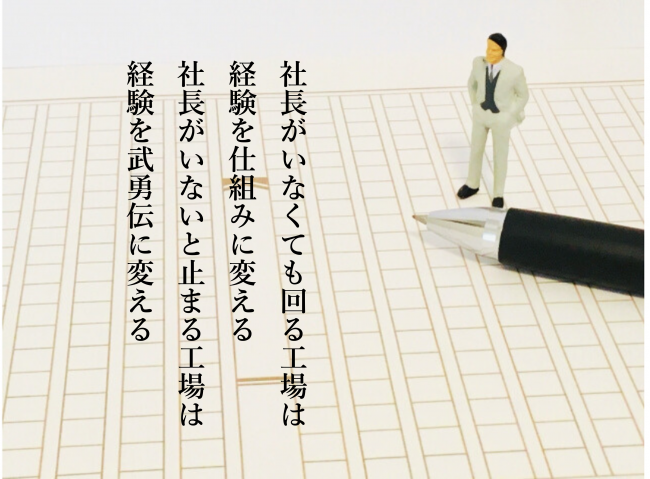
社長だけでなく、人は誰もが全く異なった人生経験をして今があります。
今日は、ある社長との出会いを通じて、「自らの経験をどう活かすか」ということについて考えさせられた話をしたいと思います。
経験が活きる
先日、久しぶりに経営者の集まりでお会いした方がいました。社長でもあり旅館の女将なのですが、行動力が普通ではありません。誰もが認めるとてもパワフルな方です。
旅館の再生だけでなく、街の再生、さらに新しい街づくりまで考えておられ、スケールの大きな方でもあります。
そのようなことができるのは、その方の人間性が大きく根幹にあることは間違いありませんが、いくら気力や根性があっても、それだけで成し遂げることができないだろうとも思いました。
工場にいるからといって、知識なし技術なしではどうしたって素人レベルのある程度のモノまでしか作れないのと同じで、旅館の再生や街づくりもそれなりに知識や技術が必要だと思うのです。
そう思いながら話を聞いていると、こんな経験を聞きました。今の経営にしっかりと行かされていることがわかりました。
学生時代に街づくりを学び、子どもたちを相手にする職業に就き、相手の意見の引き出し方、接し方を、経験だけではなく論理的に学んでおられました。
自分が働く会社の社長との様々なやり取りの中で、自然に経営者としての振る舞いや経営判断などの感覚を養っていたように見えました。
そして、女将になったのは、自分の実家ではなく嫁ぎ先です。
ですから、小さいころから女将になるべくしてそのような経験や学びを積んでこられたのではなく、たまたまそこに着地したのです。
しかし女将としての実績を伺うと、この経歴を後追いするとなるべくしてなったのではないかと思うくらい、しっかりと経営にその経験とスキルを活かしておられるのです。
後継者の立場と経験の活かし方
工場経営において、身内の後継者が後を継ぐときのパターンはこの2つではないでしょうか。・小さいころから自分はこの会社の後を継ぐと、”自然に思っている”パターン
・絶対に後を継ぐつもりはないといい、実家を出て大学に行き都会で就職するも、なんらかの理由で”仕方なく”後を継がなければならなくなったというパターン
この二つは、ポジティブなのかネガティブなのか違いがあるにせよ、自分の意思で継いでいます。
若いうちに工学部で知識や技術を身に付け、あるいは営業や経営について学び、実家の工場経営に生かす、というのはわかりやすい後継ぎルートと言いますか、仕事に就く上で分かりやすい道筋だと思います。
しかし、ネガティブパターンで実家の後を継ぐ場合、家業と全く関係のないことを学ぶ大学を出ていたり、まったく違う職種の企業に就職していたりする方が多いように思います。そんな異色の経歴を持ちながらも後継者は工場経営をするのです。
後を継いですぐは、異業種と異文化に戸惑い、何をどうすればよいか分からないことでしょう。しかし異色の経歴の何かを活かし、自分の工場経営の仕組みを構築しているはずです。
女将は身内ではありませんのでどちらにも当てはまりません。自分の意思にはないところから自分の経験やスキルを活かし、旅館内には彼女なりの仕組みを構築し、様々なステークホルダーとは彼女なりの関係性を構築されています。
工場経営者も、自らの何の経験が今の工場経営に活かすことができているのか、それを考えることが、自分が作りたい工場の仕組みに直結するのではないかと思うのです。
経験 × 論理 → 自社の仕組み
創業者は、我々後継者からは真似できない、また誰にも教えようがない「センス・感覚」を持ち経営されているように私の眼には映ります。後継者はそれをプレッシャーに感じながら、しかしこの会社を潰してはいけない、成長させなければいけないと考えています。
だからこそ、多くの後継者は「論理的な側面から」経営を学び、自分なりの経営スタイルを確立しようとするのだと思います。
このとき重要なのは、自分のこれまでの人生で身に付けてきたこと経験してきたことを、学んだ理論と紐づけすることができるかどうか、ということが非常に重要なのではないかと考えています。
経営学を学べば、教科書通りの経営になるわけです。学んだだけでは会社に個性は生まれません。
会社で作る仕組みもベースには学んだ論理的なものがあったとして、その上に社長の個性や経験が乗ることで、その会社らしい仕組みが構築されるのではないかと思うのです。あるいは逆に、社長の経験がベースとなり、その影響を受けた論理的な手法で会社の仕組みが構築されるのかもしれません。
ただ教科書通りの仕組みを構築してそれが効率的だとしても、持続可能なものになるでしょうか?残したいと思える会社になるでしょうか?
社長は、社長にしかない経験があります。社長にならなければ社長からの目線でものを見ることはできません。ですから、自らの経験を工場経営にどのように生かすことができるのか、社長目線で考えることができるのは社長だけなのです。
どんな経験も無駄にはなりません。それをどう活かすか、どのような会社を作るかということを紐づけることができれば、社長の経験や得意分野が生かされる仕組みが構築され、それは社長が長年運用する仕組みとして機能し始めるのではないでしょうか。