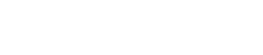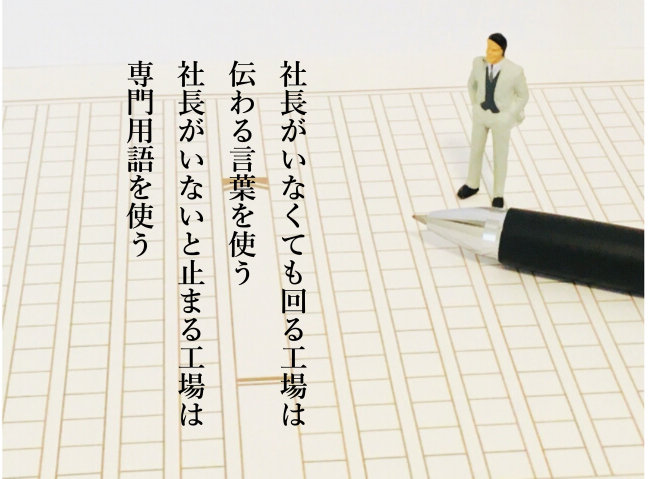
京都で出会った「手まり寿司」
先日、京都に行く機会がありました。今回は仕事とは全く関係のない訪問です。世界的な観光地でもありますが、特にどこに何を見に来たという観光でもなく、ただ久しぶりに知人に会いに来た時のことです。
京都駅を待ち合わせ場所としましたが、何年も来ない間に巨大ステーションと様変わりし、ものすごい人でごった返していました。日本人を探す方が難しいのではないかというくらいに周りからは外国語ばかりが聞こえます。
ようやく出会うことができ、昼食を取りながら話をすることになりました。
私は「手まり寿司」というものを初めていただきました。
見た目は本当に手まりのように球体で、普通の握りずしの半分くらいの大きさでしょうか。ネタは普通の握り寿司のように、魚の切り身がのっているものを想像したのですが、実際には魚は一切使われておらず、レンコン、湯葉、大葉、鴨肉などで握られきれいに盛り付けられ、食べるのももったいないように思う華やかなものでした。
確かに、京都市は海から離れていますので、昔は生の魚など食べなかったのではないでしょうか。そう考えれば納得がいきます。
お店側も、インスタ映えというものを狙っているのかもしれませんが、京都らしさを感じましたし、食べてもとてもおいしいものでした。
いただいた後の感想ですのでこのように説明できますが、それを知らずに注文し、私の前に運ばれてきた時には、瞬間的にガッカリしてしまいました。申し訳ない。
やはり、寿司と聞けば、魚のネタが乗ったものを想像していたからです。
寿司に野菜が乗っているのを見れば、私の知識と経験の範囲では、かっぱ巻き、しんこ巻き、かんぴょう巻きぐらいしか想像がつきませんでしたので、キレイな寿司だなあとは思いつつも、それほぞ食欲がそそられることはありませんでした。
食べてみてようやく、すし飯にあうように調理されていることに気付き、そのおいしさに気付くのでした。
製造現場にもある“思い込み”
話はがらりと変わりますが、この「手まり寿司」に対する思い込みのように、製造現場が何らかの思い込みにより「硬直状態」になること、変化することができないのと同じなのではないかと思ったのです。「思い込みが行動を制限する」ということです。寿司と言えば、魚のネタが乗ったものと勝手に思い込んでいます。
野菜が乗ったものもあり、そのように工夫をすれば海のない地域でもおいしいお寿司が食べられるのですが、そんなこと考えもしたことがありません。
無理やりですが、製造現場に置き換えたとき、「5S」をイメージしてみてください。
製造業で働いた経験があれば、それは、整理・整頓・清掃・清潔・躾ということは誰もが知っていることでしょう。また、それぞれがどういう行動を意味するのかも知っているでしょう。
しかし、新入社員は5Sという言葉を聞いても何のことかわかりません。どのような想像をされるのかはわかりませんが、到底、現場をきれいにすることとか、仕事をしやすい現場にする活動のことというイメージはわかないでしょう。
そうなると、掃除をやってもらうだけでも、5つのSの意味から説明する必要があり、「5Sをやってください」と言ってもすぐに実行してもらうことはできません。
そうであれば、最初から「整理・整頓・清掃・清潔・躾」という言葉で指導する方がよっぽど早く、「5Sのひとつ目のSは・・・なんだっけ?」と迷うこともありません。
それは、はじめは「まんま」とか「ちゅるちゅる」と教えられていたのに、あるタイミングから急に「ごはん」とか「うどん」と修正されるのととても似ています。赤ちゃんからすれば「最初からそう教えてくれ」と思っているかもしれません。
言葉がものの価値を上げ行動に導く
一方で「手まり寿司」の場合、その言葉が興味を引き、食べてみたいと思わせてくれます。風情があるというか京都らしい寿司のイメージがわいてきます。出てきたものはイメージしたものとは違いましたが、それはそれでなるほどと納得ができるものです。もちろん食べたらおいしい。
「手まり寿司」という名前が、私の興味を引いてくれ、食べるように導いてくれたのではないかとさえ思ってしまいます。
「5S」という言葉はどうでしょうか?新入社員がやってみたいと思ってくれるでしょうか?
5つのSのそれぞれの意味を教えられたとき、「あーそうか。それはやってみたい!」となるでしょうか?
ある工場の社長が若手社員に5Sの説明をしたとき
「あー、掃除と片付けをしろっていうことすね」
と若手社員に言われたことがあるそうです。頭の中で「単純にそういうことを言っているんじゃない・・・!整理とは・・・」と言いたくなったそうですが、逆にそれを言うことで掃除と片付けさえしなくなるんじゃないかという想像をしたそうです。
5Sを軽く言うわけではありませんが、すぐに理解でき、すぐに取り掛かることができる言葉にするということは、なかなか進まない整理・整頓や生産ラインの改善などを一気に進めることができるかもしれないのです。
製造に関する知識やスキルを磨くことも大事ですが、言葉とはとても力があるもので、「つける名前」によってその価値や行動まで変えてしまう力を持つのです。
京都訪問はちょうど「五山の送り火」の日でした。
私は今まで「大文字焼き」と言っていましたが、京都では「大文字の送り火と言いなさい」と注意されました。
その地域の人にとっては、その言葉とその行いにちゃんと意味があるからです。「送り火」と言われただけで、やっていることとその意味を一瞬にして感じることができました。
あの行事を、花火感覚で鑑賞するディナーを設定するホテルがあるそうですが、完全に外国人観光客向けにとってつけられたものだそうです。地元の人たちは憤慨しておられました。
それだけ言葉や行動には意味があり、価値があるものだと実感した、京都訪問でした。
あなたの会社では、社員が行動に移せる言葉を使えていますか?
言い方を変えるだけで、改善活動が一歩進むかもしれません。