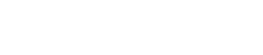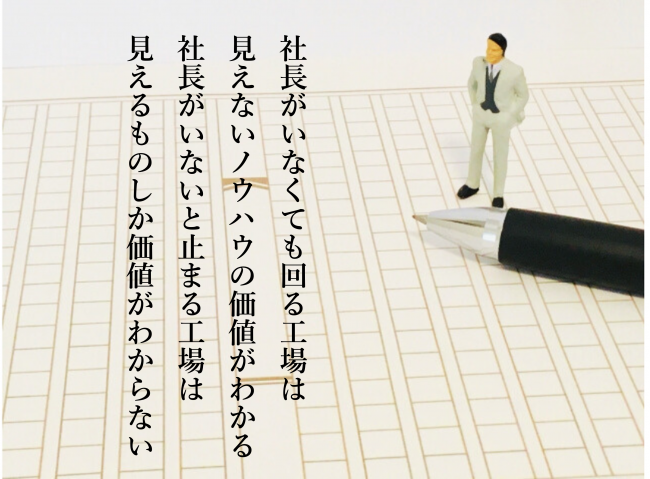
国をあげて地方の企業を強くする仕組み
最近、新聞やネットで、地方の公共団体の取り組みを目にしました。「週1副社長」プロジェクトというもので、内閣府が2015年度から始めた制度を行政がアレンジした取り組みということでした。
仕組みは、都会の大企業等に勤めている人あるいはフリーランスが、月の報酬3〜5万円程度で、地方の企業にノウハウ提供、アドバイスをするというものでした。
豊富な資金があるわけでもない、優秀な人材を確保できるわけでもない地方の企業と、副業解禁になり副収入を得たい、あるいは今まで自分が取り組んできたことを活かす場を探している人材をマッチング。
そして、地方の企業はノウハウを得て事業の課題を解決したり、事業の次のステップに進んだり、一方都会の人材は、自らのスキルアップと次の段階にステップアップし、さらに副収入を得られるというお互いにメリットのある取り組みと言われています。
さらに、都会の人たちの中には「地方の活性化に協力したい」という高い志を持った方々も多くおられるようです。その方々の活躍する舞台としても有効のようです。
成功事例も書かれていて、商品開発をするのに何をしたらよいかわからなかったところにアドバイスをもらうことができ、念願の自社商品を出すことができたとか、人事評価制度の構築のアドバイスをもらうことができたとか、他の企業もどんどん活用してはどうかと進める記事でした。
どんな取り組みにも良いところもあれば、悪いところもあるものです。
何に対しても斜めから見てしまう私には、この取り組みに違和感を感じ、すんなりと良い取り組みだと受け入れることができませんでした。
粗探しするわけではありませんが、私にはこの事業が地方の企業の弱体化により繋がっていってしまうのではないかと懸念を持たずにはいられません。
見えないものに価値を感じる能力の差
まず前提条件として、地方の企業に、都会の大企業に比べノウハウがないということは否定はしません。しかし、ノウハウがない理由はなんでしょうか?
企業のノウハウの成り立ち方を考えてみれば、なぜその企業にノウハウがないのか分かります。
ノウハウとは、企業が創業時から個々の知識やスキルを寄せ集め、ミックスして何かを作り上げる過程で生まれてきたものです。それが製品だったりサービスだったりいろいろな形になり世の中に出てお金になるわけです。
それの最たるものが特許でしょう。自社の積み上げてきたノウハウによりこんな新しい技術がある、他の技術とは違うということを公式に認めてもらっていて、その技術を簡単に他社に持って行かれないようにする仕組みです。ノウハウの大切さを象徴するものでしょう。
話を元に戻し、地方の企業にノウハウがないということは、それを持つ人がいないということであり、またそれを持つ者を雇用することができないということでもあり、そして、その「投資」をして来なかったということが言えないでしょうか。
新商品を出し続けノウハウを蓄積してきた企業、社員が働きやすい環境にするために考え続けてきた企業、設備の安定稼働のために知恵を絞り続けてきた企業、様々な問題に対しその都度「必要な投資」をし解決することでノウハウを蓄積してきたのです。
地方の企業では、そのような取り組みや投資をおろそかにし、目先の売り上げだけに注力してきてしまった、という側面はないでしょうか。
例えば組織改革や人事評価制度の構築についてです。
そのようなことに取り組むのは、大企業であれば人事部などがありその部署の社員が専門的に取り組んでいるでしょう。社員の成長、社員の働く環境、会社の経営方針に対してどんな人材が必要なのか、様々なことを戦略的に考えて実行し、ノウハウを蓄積してきたことでしょう。
一方で、地方で組織図上その機能を持つ企業は、ないに等しいでしょう。
しかし人事に関することを何も考えず事業を継続することは絶対に不可能です。したがって必ず誰かがそれに匹敵することを行っているはずです。
そうです。その多くは社長や奥さんたちが他の業務と兼任しています。そのようなことをやってくれるベテランの管理者、工場長がいれば御の字です。
さらに、その役割を持ちつつも「ノウハウ」を有して行なっているわけではありません。「人柄」だけで何とかやっています。それを人事の仕事と考えたこともないかもしれません。
このような仕事のやり方をしているから、人事評価が「社長のさじ加減」「ブラックボックス」と言われてしまうのです。
この仕事を重要な仕事と考え、言語化しているでしょうか?問題解決したとき何らかの形でノウハウとして蓄積されているでしょうか?そのようなことをすることに時間やお金をかける、いわゆる「投資」をして来たでしょうか?
多くの会社が、問題が収束すれば考えなくなり、3か月後、半年後、1年後にまた同じ問題に困らなければならない状況を繰り返しています。
この投資をしているかしていないかが、都会の大企業と地方の企業の大きな違いだと考えています。
現場の生産の業務に比べ圧倒的に工数の少ない人事の業務にどれだけの投資が必要か。生産しなければ売り上げがないと考えると、人事に関することに投資をするくらいなら・・・と考えてしまうかもしれません。
しかし、そのようなノウハウを持った社員を雇うことと考えた時、それなりの年収は払わなければならないことは想像がつくでしょう。
それなのに、行政のこの取り組みにより、この重要なノウハウを月3〜5万円で売ろうとしている。しかも、たったそれだけの投資で同じような効果を得ようとしているということなのです。
私はこのことは、社会の仕組み、さまざまなものの価値基準からして大きく間違っていると考えています。
行政やメディアは、成功事例しか伝えないでしょう。それを発信し続ければ、組織改革や人事評価制度の構築は、月に3〜5万円程度で都会の人が片手間でできるものという、「付加価値」というものの価値がわからない社会ができてしまうということが想像されてしまいます。
ノウハウの全てを出さず、続きは正規料金で・・・という仕組みだとしたら、それは地方の企業側は注意しておかなければならない危険な仕組みです。都会の商売の仕組みにまんまとはまっていると言わざるを得ません。
ほとんどの工場経営者は、数千万する生産設備を導入するときは、しっかり見積もりを取り、回収できるかを計算し投資をすると思います。お試しで1か月くらい工場に設置してみてダメだったら撤去して、なんていうことはあり得ません。
同じように人事の仕組みを導入するのであれば、それくらいの心構えが必要ではないでしょうか。依頼先が、都会で働く人でもコンサルタントでも構いません。これだけの知識やノウハウを提供してもらう、仕組みの構築の手助けをしてもらう、そのために人の拘束をする、ということを考えればそれなりの額を払うことは腹に据えて決めなければいけません。
ビジネスの基本は対等なやり取り
そして、もっと重要なのは、このマッチングの取り組みで、地方の企業が都会のビジネスマンと対等な立場でビジネスを行うことができるか、ということだと私は考えています。ノウハウを提供する側が強く、教えてもらう側は弱い、都会の人が上で地方の企業が下というのも違います。
ビジネスとは対等に行わなければいけません。
安く、それっぽいノウハウを得て、前よりよくなったとして、自社のノウハウと言い切れるでしょうか?そのノウハウを武器に、堂々と取引先と対等にやり取りできる企業になるでしょうか?
ノウハウとは、言語化され再現性のあるもので、人による時間と労力により築きあげられたものであり、そう簡単に作られるものではありません。そのノウハウを安く買った会社が、そのノウハウを使い出来上がった商品があったとして、堂々と正当な値段をつけて取引先や市場に出すことができるでしょうか?取引先や市場は提示された価格を対等な目線で見るでしょうか?値切ることしかしないでしょう。
逆に、自社が人と時間をかけノウハウを蓄積しようやく出来上がった商品を、市場価格に見合わない価格で買おうとする取引先があったらどう思うでしょうか・・・。
資材価格の高騰や光熱費の高騰など製造原価の高騰を理由にした値上げ交渉は、以前より成功していると聞きます。行政側も仕事を出す側の企業に目を光らせています。
その一方で、依然として人事や労務に関する費用はなかなか単価に反映するのは困難です。社員の給与を上げることは、自社努力で何とかするものだという考えが根付いているためです。最低賃金の設定額や給与額がどんどん上昇する中、この交渉が成功しないことは本当に死活問題です。
資材の価格、人件費、光熱費などの目に見える費用だけでなく、人事や労務、組織改革による企業価値の向上など「ノウハウ」という見えない価値、費用について、自社がその価値をわかっていなければ、相手企業に説明することも難しく、単価交渉も厳しくなるでしょう。
非常に考えさせられる行政の事業の話でした。