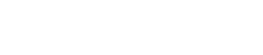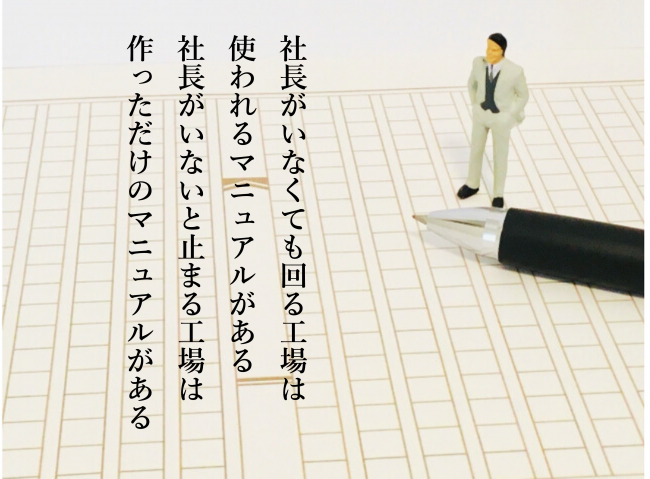
属人化が招いた「見えない作業」
ベテラン社員のAさんが退職されるとのことで、現場の作業の引継ぎのために、「自分がやっている作業マニュアルを作っておいてほしい。」と社長は依頼したそうです。Aさんは、生産ラインに直接入ることななく、倉庫で業務することがほとんどで、これまでほとんどの作業を一人で行ってきました。そのため、これまで特別に作業を誰かに引き継ぐなどのようなことを行ったことがありません。所謂、属人化が起こっていたのです。
あるとすれば、自分が休みに入る前に気の知れた人に頼みごとをする程度で、作業指導といえるようなものではありません。「休みの間に○○しておいて」とお願いするくらい。その内容も口頭で伝えれば済むようなことでしたので、メモ書きしておくことはあってもマニュアルなど仰々しいものを作ったことはありませんでした。
一方で現場からは「Aさん、倉庫に居るようだけど実際に何しているかわからない」「でも、自分たちが作業するときには倉庫で現物を見ればわかるので、マニュアルなんかなくても・・・」とマニュアルがなくても困らない、という様子。
社長からマニュアル作成を依頼したものの、結局は現場の必要に応じてマニュアル作成を行うということとなりました。
Aさん退職後、1か月くらいしたところでクレームがあったと報告があったそうです。
内容はこうです。-------------------------------------------------------------------------------
納品された製品の中に、「梱包状態が、指定された納品時の仕様になっていないものがあった」とのことでした。
倉庫には、製品の完成品置き場を作っているのですが、生産ラインの最終工程が完了したら、現場の作業者がそこにその製品を持ってくるそうです。そしてAさんが納品可能な梱包状態になっているかどうか確認し、トラックに積むものを置くスペースに移動するそうです。
どうやら、この「納品可能な梱包状態になっているか」「トラックに積むものを置くスペースに移動」という作業は、Aさんが独自に作成されたルールの様で、そして誰にもそのルールが伝えられていなかったのです。
そして、納品状態が確認されないまま出荷されてしまった・・・。
作業マニュアルの中身より必要なこと
この作業について、社長や現場がきちんした引継ぎを行っていなかった、その確認がなされていなかったと言ってしまえばそれまでです。しかし、それでは引継ぎ時の手順をまとめて終わりになってしまうでしょう。
さらに最悪の場合、「Aさんが何も教えてくれなかった」と退職したAさんのせいにして終わりになりかねません。
このようなことが起こった最大の原因は、「作業マニュアル」の運用の仕方、に問題があると言えます。
作業マニュアルというと、みなさんはどのように使うものと決めていますか?
作業をしたことない人が、これを見ながら作業するために必要なものでしょうか?
作業指導の時にテキストとして使用するものでしょうか?
あるいは他の使い方でしょうか?
そもそも、この使い方(運用の仕方)が定義されていなければ、作業マニュアルは機能しません。
「作業マニュアル」とは、作業をするときにこれを見ながら順を追って作業するもの、と暗黙の了解の理解がされていました。だれも正確な使い方を説明できなかったのです。
そしてその理解はいわば、プラモデルの組立説明書という位置付けだったのかもしれません。プラモデル作りはいつでも初見での組み立てになりますので、手順を確認しながら出ないと作れません。
しかし、倉庫の材料を現場に出す、現場で使った材料を倉庫に戻す、完成品を倉庫に移動する・・・など作業一つ一つについては、はじめに教えてもらう時にマニュアルを使ったとしても、何度も同じ作業を繰り返すわけですので、覚えてしまえばマニュアルを見なくても作業はできてしまいます。むしろ、マニュアルを見なくても作業できるように覚えてね、と指導をするでしょう。
このように暗黙の了解で理解されていた作業マニュアルの使い方と、本来の現場での用途が全く異なっていたため、マニュアルの作成そのものが不要になってしまっていたのだと考えられます。
事実、今回クレームが発生した、その作業については、作業の有無すらマニュアルに記載されていませんでした。したがって、現場の社員にとっては寝耳に水「そんな作業あったの?」という状態でしょう。
しかしながら、こういうことがクレーム発生の大きな要因となることが多いのです。
作業マニュアルは、どんなに手の込んだ資料を作っても、IT化して作りやすく閲覧しやすくなっても、なぜ必要なのか、どのような場面で使われるものなのか、という運用ルールを決めておかなければ、絶対に使われなくなっていくでしょう。
また、作業者が、いつまでも作業手順書を見なければ作業できないという状態であるなら、むしろその方がその作業者は大丈夫か?と作業スキルに疑問を持つでしょう。
そうすると、「作業マニュアルを見なくても作業ができるようになること」という一つのスキル習得の基準が生まれます。必要事項の記入が漏れていれば、責任問題に発展します。話は反れますが、作業マニュアルを作ることで、社員の評価基準にも影響が及んでくるのです。
マニュアル通りの作業手順でクレーム発生につながるようなことはないか、作業者がマニュアル通りに作業を行っているかなど、手順や作業の見直しはたびたび行っていることでしょう。
しかし、その「確認が形骸化」していないでしょうか。そして「ISOに必要だから作る」という目的を見失ったものとなっていないでしょうか。
「作業マニュアルを作るほどの作業でもない」と言わせてしまっていないでしょうか。あなたの職場では、作業マニュアルは本当に「使われる」ものになっていますか?