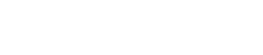1.png)
いま、工場経営はかつてないほどの試練に直面しています。
資材価格の高騰、電気・燃料代の上昇、設備の維持費、低迷した経済を脱するためとはいえ、物価高騰により何もかもが値上がりし、工場経営の維持も非常に窮屈なものとなっています。
そして人件費の高騰。個人の手取りが増えるのは良いことですが、工場経営をより難しいものとし、もはや経営者の努力だけでは乗り越えられない時代が来ています。工場の存続も経営者の手取りも今後どうなってしまうのでしょうか。
そのような経営環境の中、工場の経営改善を今までのように考えていたのでは世の中の変化について行けない状況になってきています。社長ひとりがどんなにがんばっても限界があります。自社内の能力を考えても同じです。
そんな時に知恵を借りる先がコンサルタントだったりします。
コンサルタントにも様々な人がいて、経営全般を扱う経営コンサルタント、組織や風土改革を扱うコンサルタント、人事評価の導入を支援する人事コンサルタントやキャリアコンサルタント、財務面の支援をする財務コンサルタント、ITの導入支援をするITコンサルタントなど、大手のコンサルティングファームから一匹狼のコンサルタント、真面目なコンサルタントやよくわからない怪しいコンサルタントなどなど、企業の課題に応じて選ぶ必要があります。
こうした厳しい経営環境の中で、現場改善コンサルタントに支援を求める工場経営者が増えています。生産現場は工場の収益に直結する重要な場所です。ここで粗利が確保できなければ事業存続はありません。
そこで今回は、現場改善コンサルタントがどのような支援を行うのか、そしてコンサルタントがいなくても自社で取り組める改善のフレームワークについて、実例を交えてご紹介します。
⇒「工場経営自動化コンサルティング」についてのお問い合わせはこちら
現場改善のコンサルとは?
これまで、私は自社工場の現場のリアルな課題に向き合い解決しながら経営を行ってきました。その傍ら、金属加工や板金加工、印刷業、電子部品組み立て工場など様々な工場の現場で改善支援を行ってきた経験から、単なる理論ではなく、実践に基づいた現場作業者が取り組むことができる改善支援を行うことを大切にしてコンサルティングを行っています。当社では、工場経営者向けに「工場経営自動化コンサルティング」を提供しています。現場の作業工数や設備の停止時間を短縮することだけにとどまらず、経営者が次のビジネス展開に専念できるよう、現場を社員に任せられる仕組みづくりを支援しています。
現場改善のコンサルとは、直接作業と言われる売り上げに直結する部分をいかに効率よく行うか、そしてそれ以外の間接作業を「無駄」と位置付け、いかにその時間を短縮するかにフォーカスを当て、生産性の向上を図る取り組みです。
※関連記事:製造現場のムダを無くし効率化するには?現役経営者が事例を元に解説
ただし、達成される作業工数の削減はあくまでも手段であり目標値で、現場の作業者だけでなく、管理者、経営者とのコミュニケーションにより、作業工数の削減という数値が、売上の増加、経費の節減、利益の向上などといった経営改善にどう繋げるかを明確にすることが重要です。
改善の取り組みが工場の仕組みとして定着することで「品質向上」「納期順守」「安全性向上」「社員の成長」など、企業の事業継続と持続的な成長に結びつく成果が得られます。
⇒さくらブルーのコンサルティングメニューの詳細はこちら
現場改善のコンサル内容
現場改善のコンサルティングでは、単なる作業効率の向上にとどまらず、現場のムダを見える化し、社員が自ら改善に取り組める仕組みづくりを支援します。現場確認、課題抽出:作業の観察やヒアリング、データ分析を通じて現場の現状を把握し、課題を抽出します。 データが不十分な場合は、IT導入などによりデータ分析ができる環境を整えることも行います。
改善目標の設定:次に、生産性、品質、納期、コスト、安全性などのKPIを設定し、改善の方向性を明確にします。設定するKPIは、あくまでも経営改善の成果(KGI)につながる論理的に説明可能な値にする必要があります。単に作業者の作業が楽になっただけで経営数値に何も変化がなければ、目的のない改善になってしまいます。
改善施策の立案・実行支援:業務プロセスの見直しやレイアウト変更、ITツールの導入など、現場に即した具体的な提案を行います。
改善の仕組みの定着支援:この活動が、コンサルタントが関与している時だけの一過性のものになってしまわないよう、ワークショップやOJTを行ったり、経営方針に落とし込み会社としての取り組みとなるよう支援します。
効果検証と仕組み化:改善実施後は、Before/Afterの比較やKPIによる効果検証を行い、成果を定量的に評価します。定量的に評価するためには数値の蓄積が必要不可欠なため、必要に応じてITツールの導入を行い経過を観察できる環境を整えます。
これらの取り組みが現場だけで行うことができるよう支援することが、現場改善コンサルタントの重要な役割です。
※関連記事:製造現場のあるべき姿とは?経営経験を元に理想と現実を解説
工場の種類別に見る改善アプローチの実践例
現場改善と一口に言っても、工場の業種によって課題の種類や改善の切り口は大きく異なります。ここでは、私がこれまで支援してきた代表的な工場の種類ごとに、よくある課題と改善の視点をご紹介します。【金属加工工場(マシニングセンターなど)】
この業種では、段取り時間の長さや工具管理の煩雑さ、加工順序の最適化、設備稼働率の低さが主な課題として挙げられます。
改善にはIE手法による作業分析(時間研究・動作分析)や、TOC(制約理論)によるボトルネック工程の特定が有効です。また、加工プログラムの標準化・自動化(CAM連携)や、OEE分析による稼働率の見える化も重要な取り組みです。
※IE(Industrial Engineering)手法
作業にかかる時間の測定(時間研究)や作業者の動きの無駄を見つける(動作分析)などを通じて、作業の標準化や生産性向上を図ります。 例えば、段取り替え作業の動画を撮り、映像を分析して作業時間の測定を行い、一つ一つの作業の無駄を排除したり、標準的な作業時間の設定をしたりして、効率が良い作業に改善していきます。 同じように時間分析をする手法に、※SMED(Single-Minute Exchange of Die)による「段取り時間短縮」を目的とした分析手法があります。
段取り作業に特化したもので、動画の分析により、設備停止中にしかできない「内段取り」、設備稼働中にできる「外段取り」に分類し、専用治具を使って内段取り時間を短くしたり、段取り替え作業前に外段取りに分類される作業を済ませることで、設備の停止時間を少なくする取り組みです。
※TOC(Theory of Constraints:制約理論)
全体の生産性を制限している「ボトルネック工程」を特定し、そこを重点的に改善することで、工場全体のパフォーマンスを向上させる考え方です。
例えば、ボトルネック工程が特定できたら、その工程は1日中作業者が常に張り付いていられるよう人員配置を検討したりします。
※OEE分析(Overall Equipment Effectiveness:設備総合効率)
設備の稼働率を「可動率」「性能」「品質」の3つの観点から数値化する指標です。
例えば、設備がどれだけ稼働していたか(可動率)、計画通りのスピードで動いていたか(性能)、不良品がどれだけ出たか(品質)などを総合的に評価し、改善ポイントを明確にします。
【薄板板金加工工場(ブレーキプレス、レーザー加工機等)】
材料が非常に大きくなることが多い業種です。材料の取り回しや加工順序の非効率、段取り替えの頻度が課題となりやすい業種です。レイアウト改善による動線短縮や、VSM(バリューストリームマッピング)による加工フローの可視化が効果的です。工程の統合・再設計(BPR)や、搬送工程の自動化・ロボット導入も検討の余地があります。
※VSM(バリューストリームマッピング)
製品やサービスが顧客に届くまでの一連の流れ(バリューストリーム)を図式化する手法です。工程ごとの作業時間、待ち時間、在庫、情報の流れなどを可視化することで、無駄を発見し、改善ポイントを明確にします。特に複数工程にまたがる業務の効率化に有効です。
例えば、製品が完成するまでの工程、受注→生産指示→材料準備→レーザー加工機→ブレーキプレス→組み立て→溶接→研磨→梱包→出荷、という流れがあったとして、これを図式化し、肯定感の無駄な待ち時間や在庫、情報の流れの非効率を洗い出します。これにより改善すべきポイントが明確になり、工程全体の最適化が可能になります。
※BPR**(Business Process Reengineering:業務プロセス再設計)**
既存の業務の流れを根本から見直し、ゼロベースで再設計する手法です。単なる部分最適ではなく、業務全体の構造や役割分担、IT活用などを含めて抜本的に改善することで、大幅な効率化やコスト削減を目指します。業務の流れを図式化し時間や情報の流れが見えるようにする点ではVSMと似ています。
現場の作業者だけで取り組むようなものではなく、経営改革を前提とした全社的な取り組みとなります。
【電子部品組み立て工場】
部品の取り違えや作業ミス、ラインバランスの不均衡が課題です。IE手法によるラインバランシングや、ポカよけ(ミス防止)による品質確保、デジタル作業指示書の導入が有効です。QC7つ道具やシックスシグマによる品質管理強化も欠かせません。
※QC七つ道具
現場で起きている問題を見える化し、原因を探るためのQC(品質管理)の基本的な分析ツールで、現場での問題解決に役立ちます。具体的には以下の7つです:
パレート図(重要な問題の特定):不良の多い順に並べて、重点改善箇所を特定します。
特性要因図(原因分析):「なぜ不良が起きるのか?」を、人・設備・方法・材料などの観点で整理します。
グラフ(傾向の把握):取得した数値をわかりやすく図式化し、改善前後の比較などに活用します。
チェックシート(データ収集):不良の種類と発生数を記録したり、あらかじめわかっている確認重点箇所の経過観察に使用します。
ヒストグラム(分布の確認):不良品の寸法などのばらつきを確認します。
散布図(相関関係の分析):温度や湿度など設定したある条件と不良率の関係性を分析します。
管理図(工程の安定性の確認):上限値下限値の設定をして工程が安定しているかを時系列で確認します。
これらは、現場の作業者でも使えるシンプルなツールで、改善活動の第一歩として非常に有効です。
※シックスシグマ
Six Sigmaは、工程のばらつきを統計的に分析し、不良率を極限まで減らすことを目的とした品質改善手法です。「DMAIC(Define, Measure, Analyze, Improve, Control)」という5つのステップで進められ、改善活動を論理的・定量的に進めることができます。特に、品質に厳しい業界や工程の安定性が求められる現場で効果を発揮します。
寸法のばらつきが多い部品加工を例にすると、
寸法データを収集し、標準偏差(σ)を計算します
設計上の許容範囲(±3σ)に対して、実際のばらつきが収まっているかを確認します。
ばらつきが大きい場合は、設備の精度や作業手順を見直します。
工程能力指数 Cp、Cpk の指標を使って、工程がどれだけ安定しているかを数値で評価します。
※DMAIC(Define, Measure, Analyze, Improve, Control)
Define(定義)
改善したい課題を明確にする(例:設備停止時間の削減)
Measure(測定)
現状のデータを収集(例:停止時間の頻度と長さ)
Analyze(分析)
原因を特定(例:故障、段取り、材料待ちなど)
Improve(改善)
対策を実施(例:予防保全の強化、段取り標準化)
Control(管理)
改善が定着するように管理(例:定期点検の仕組み化)
【印刷業】
印刷業では、ジョブの切り替えの頻度や色調整の手間、紙のロスが課題です。リーン・シックス・シグマを活用して品質ばらつきを低減し、5Sによる資材・インクの管理の効率化をはかります。作業標準化と教育体制の強化、生産スケジューリングの最適化も重要です。
※リーン・シックス・シグマ(Lean Six Sigma)
Lean(ムダの排除)とSix Sigma(品質のばらつきの低減)を組み合わせた改善手法です。Leanでは「不要な工程や待ち時間」をなくし、Six Sigmaでは「不良やミスの発生率」を統計的に分析して改善します。工程の効率化と品質向上を同時に実現できるため、製造業だけでなくサービス業でも広く活用されています。
前述のDMAICに沿って、
Define(定義)
Lean:無駄な工程や作業を洗い出す
Six Sigma:品質問題やばらつきのある工程を特定
Measure(測定)
Lean:作業時間、待ち時間などを測定
Six Sigma:不良率、寸法ばらつきなどを測定
Analyze(分析)
Lean:なぜムダが発生しているかを分析
Six Sigma:ばらつきの原因を統計的に分析
Improve(改善)
Lean:動線改善、段取り短縮などを実施
Six Sigma:工程能力向上、標準化などを実施
Control(管理)
Lean:改善が定着する仕組みを作る
Six Sigma:品質が安定するように管理図などで監視
現場改善の進め方と設備停止時間削減の実践
1.png)
前の項で業種別の改善とその中で使える改善手法の説明を行いました。
しかし、ある特定の改善手法を現場に当てはめようとすると、現場と教科書的な理論の乖離が起こり、無理が生じて改善どころか文字の当てはめ作業になりかねません。
現場改善を成功させるには、場当たり的な対応ではなく体系的な進め方が必要です。
ここでは、改善の王道ステップに沿って、設備の停止時間の削減をテーマにどのような改善手法を活用するかを具体的に解説します。(あくまでも一例です)
1.現状把握とデータ収集
まずは、設備停止の実態を把握することから始めます。停止時間の記録(日時、原因、影響範囲)を収集し、稼働率を測定します。
<活用手法>
・可動率・性能・品質の三要素から設備の総合効率を数値化します
・チェックシートで停止の種類と頻度を記録します
・グラフなどを作成し、傾向の分析と見える化を行います
2.課題の特定と優先順位付け
収集したデータを元に、停止原因を分類し、頻度や影響度の高いものから優先的に改善対象を選定します。
<活用手法>
・パレート図:重要な停止原因を特定します(段取り替え、調整、故障、不具合、材料待ち、人待ち、清掃、メンテナンス等)
・特性要因図:原因の構造を整理します
・TOC:ボトルネック工程の特定と改善優先順位の設定をします
3.理想状態の定義
停止時間が最小化された理想的な状態を定義します。どの工程がどのように改善されるべきか、目指すべきKPIを設定します。
<活用手法>
・VSM:工程全体の流れを図式化し、無駄を可視化します
・BPR:工程の統合や役割分担の見直しを行います
・KPI設計:稼働率、平均故障時間(MTBF)、平均修復時間(MTTR)などを設定
4.改善案の立案と実行
具体的な改善策を立案し、現場で実行します。
<活用手法>(実行しやすいもの)
・SMED(段取り時間短縮):内段取り外段取りの分離と標準化を行います
・IE手法(時間研究・動作分析):作業の順序や役割分担の最適化
・リーン・シックス・シグマ:無駄の排除とばらつきの低減を同時に実施します
段取り替え時間の短縮、予防保全の強化、作業標準化などが中心になります。
前述のパレート図:段取り替え、調整、故障、不具合、材料待ち、人待ち、清掃、メンテナンス等、のうち、段取り替え・材料待ち・人待ち・清掃・メンテナンス等の作業はこれらの手法の活用で時間削減を見込めます。
しかし、調整・故障・不具合は生産技術的な領域になります。解決する技術があるかどうか、さらに解決案を導き出す知識や発想力があるかどうか、が重要になってきますので、さらに調査、分析が必要になります。
5.効果検証と標準化
改善後の状態をBefore/Afterで比較し、KPIで効果を定量的に評価します。改善が一過性で終わらないよう、標準化と仕組み化を行います。
<活用手法>
・管理図(QC七つ道具):工程の安定性を時系列で監視
・Cpk(工程能力指数):ばらつきの改善度を数値で評価
・IT化によるデータ監視環境の構築や記録・通知などの自動化
6.継続的改善の仕組み化
改善活動が現場で自走できるよう、改善提案制度や教育体制、定期レビューの仕組みを構築します。
・取り組み内容のデータベース化(工場のノウハウ)
・成功事例の横展開
・IT化による報告・記録の自動化やデータ閲覧・分析環境の構築
現場改善をコンサルに依頼する場合に気を付けること
改善手法はあくまで道具です。しかし、改善の知識を持たないままの現場作業者が改善活動を行っても、整理整頓レベルで終わるようなものしか改善提案が出ないということはよくあることで、当然そのようなレベルの取り組みでは設備の稼働率が上昇したり、段取り時間が短縮したり、まして経営数値の改善に直結するような取り組みになることはほぼありません。道具とはいえ使いこなすことができれば効果は絶大です。その効果を出すために重要なのは、それをどう使い、どう現場に定着させるか。ここからは、工場経営者として押さえておきたい改善活動の進め方と、具体的な実践例をご紹介します。
※関連記事:製造業の課題を乗り越える解決策!現役経営者が提言する中小企業が取るべき実践的アプローチ
活動の位置づけと活動体制
現場改善をコンサルタントが関与しているときだけの一過性のものにしないためには、「現場任せ」ではなく、経営方針の一部として明確に位置付けることが重要です。経営者の支援があってこそ経営改善に結びつくものとなり、そして継続的に機能するものとなります。したがって、工場経営者は、「なぜ改善が必要なのか」「改善を行った結果どんな工場になるのか」と明確に示し、作業者が日頃行っている生産業務と同等に取り組まなければならないことを理解してもらうことが必要です。
また、経営者が直接作業者と取り組むことは、それは経営者の仕事ではありません。現場のリーダー、管理者の役割を明確にして権限を与え、現場だけで実行できる環境づくりが必要です。
データ取得、分析環境
改善提案を求めると、決まって「その時に困っていること」が多数あがってきます。改善が必要な事案であることは間違いないのかもしれませんが、提案者の思いつき、感覚、経験則だけに基づいた提案であることが多いため、周囲の理解が得られにくく取り組んでも成果につながらないことが少なくありません。また、論理的な根拠がない状態の提案を経営者がそのまま受け入れ、率先して進めようとしてはいけません。だからこそ、日ごろから異常に気付くことができる環境、または困ったことが発生したときに論理的に説明できる環境が必要です。
そこで効果を発揮するのがIT化によるデータ取得と分析環境の整備です。
日々データを取得し監視できる体制があれば、改善に着手しやすく、前後のデータ比較から効果の確認も容易になり、改善サイクルが高速化します。
また感覚的な困りごともデータによる説明があれば、周囲への説明や社長決裁も容易になるでしょう。
このようにデータを活用できる環境を整えることが、データに基づいてコミュニケーションを取る環境となり、ベテラン社員や特定のわかっている人だけの改善ではなく、全作業者が改善に取り組むことができる環境が整います。
「なにからIT化をすればよいか分からない」という場合は、このようなところから着手するとよいかもしれません。
※関連記事:製造業における属人化とは?問題点と経営者がやるべき対策方法を解説
個々の能力と評価と報酬
改善を行うには、言い換えると改善手法を使いこなすには、ある程度の個人の能力は必要です。どんなに教育を行っても理解度に差が出てきてしまうため、そのため個人の改善能力の差が出てくることは当然です。その差を考慮せず、提案制度、表彰制度を導入し提案者には報酬を出すという仕組みの導入は、特定の社員に報酬が偏ったり、改善活動が一部の人の“特別な業務”になってしまうことがあります。そうなっては、現場全体の改善文化が育たず、経営方針と乖離した取り組みになってしまうこともあります。これは評価制度を設定したことが悪い方に振れてしまった場合の一例ですが、重要なのは、個人の能力差を踏まえた教育環境の整備と、改善活動が全員にとって「日常業務の一部」として根付くような仕組みづくりです。報酬や評価は、結果だけでなく、取り組みの姿勢やプロセスにも目を向けることが求められます。
まとめ
本記事では、現場改善の基本的な考え方から、業種別の改善アプローチ、改善の進め方と具体的な実践例までを紹介してきました。重要なのは、改善活動を「一部の人の努力」や「一時的な取り組み」にとどめず、工場の仕組みとして定着させることです。社員自らが考え、動き、改善を進められる現場ができれば、経営者は次のビジネス展開に集中することができるようになります。
さくらブルーでは、「工場経営自動化コンサルティング」で現場を社員に任せ、社長が次のビジネス展開に専念できる仕組み構築のノウハウを提供しています。
⇒セミナーやコンサルに関するお問い合わせはこちら