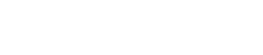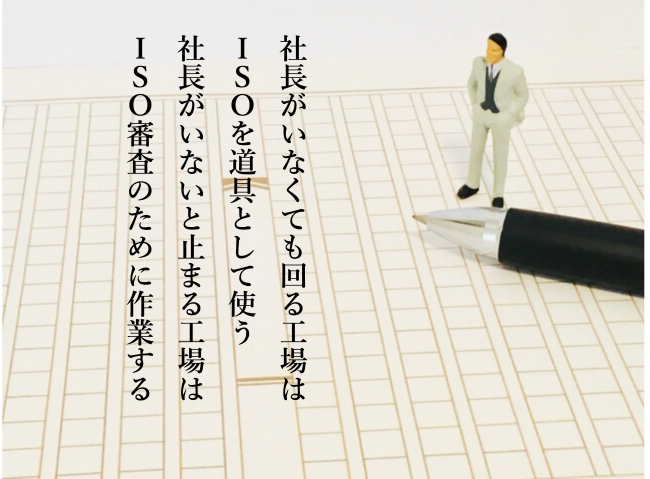
ISO認証は現場改善の味方か、それとも足かせか?
ある工場経営者のつぶやきです。「来週、ISO9001認証の更新審査があって、それまでに準備しておかないといけない資料とかあって、最近はずっと工場にこもりっきりだよ・・・」
みなさんはこのつぶやきを聞いてどう思われるでしょうか?
日本能率協会の調査では、ISO取得理由で最も多かったのは、「自社の経営体質やマネジメントのレベルを高めるため」(84.2%)というのが突出して高かったそうです。
しかし、私が現場で接する工場経営者の声からは、むしろ2番目の「取引先や親会社等からの要請があったため」(38.6%)が主な理由であるという印象を強く受けます。
つぶやきを聞いた後でバイアスがかかっているかもしれませんが、このアンケート結果をみなさんはどう思われるでしょうか?
工場に訪問させていただき、たびたび聞く困りごととして、「ISOのために必要な資料の作成や管理が大変。無駄ではないか?と思うような作業も認証を受けてしまったために変えることに躊躇する」というものです。
その結果、冒頭のつぶやきの様な目的の見えない作業に追われなければならなくなっているのです。
ISO認証の本来の目的と、運用の落とし穴
ISO9001は工場で最も取得件数が多い規格のようです。製品やサービスの品質を安定させ、顧客満足を高めるための仕組みを社内に構築するためのもので、多くの製造業では、品質保証体制の整備のために使われているのではないでしょうか。この認証取得により、工場をブランド化したり、顧客から信頼を得る材料として、営業活動、外部へのアピールとして使われることもあるでしょう。
そしてこの中身は、業務の標準化、手順化、記録を行い、製造にかかわる人、モノ、情報などリソースの管理を行うことで完成品になるまでのプロセスの管理を行い、完成品を保証する体制を作るものです。
一方で、ISO認証を取得していなかったらこの管理が不要かといえばそうではありませんし、認証取得していなければ物を作ってはいけないということもありません。
要は、「どのようなスタンスで、どのような目的でISO認証取得をするのか?」ということがとても重要だということです。
取引先からの要求や入札条件として求められていれば、取得しなければ事業継続が難しい場合もあります。この場合は、製品やサービスの品質を安定させ、顧客満足を高めるための仕組みを社内に構築するためのものというISO本来の役割から反れた目的で利用されてしまうかもしれません。
不適合になれば認証継続できないため、審査官に指摘されないよう資料を準備し、手間な作業があっても無難にやっておいた方がいい、と業務改善が進まないこともあります。
審査機関側からしてみれば、ISO認証をそのような運用をされてしまうことは本心ではないでしょう。年中審査している人達ですから、そのような工場のやり方は見抜いておられることと思います。
それでも審査基準に照らすと違反しているわけではなく、本来不要な作業である可能性が高いにもかかわらず、審査を受ける側の工場がそのような状態で審査に臨んできているのだから不適合とする理由はない・・・。
これは、これまで審査を受ける側の私の経験で感じる推測ではありますが、冒頭の社長のつぶやきや違和感を感じるアンケート結果、審査官から受ける指摘やアドバイス、それらを考えればそう外れてはいないと思います。
前にも述べましたが、ISO認証取得は任意です。そして社内に業務の仕組みを作るための一つのツールでしかありません。工場がどういう意思をもってどういう目的で選択し取得するか、がとても重要です。
多くの工場が、業務改善や現場改善、その他にも事業の継続や成長のために、日々様々な取り組みを行っていることでしょう。
しかしその一方で、ISO認証の継続を目的とした業務フローや作業手順が、現場の改善活動と乖離してしまっているケースも少なくありません。
業務改善に取り組んでいるはずなのに、「ISOのために必要だから」と、現場では無駄だと感じられている作業をやめることができずにいる・・・これは、社内の足並みがそろっていない状態であり、改善活動とISO運用が互いに足の引っ張り合いをしているようなものです。
改善とISO運用の一貫性
本来、ISO認証は社内の仕組みを整えるための枠組みです。にもかかわらず、その運用が目的化してしまうことで、改善が進まない状態になっているとしたら、それは本末転倒です。このような状況を打開するために、当社が提案しているのが「工場経営の自動化」です。業務改善やその標準化や記録の仕組みを構築し、手作業極力なくしシステムで支えることで、ISOの運用の効率化とISOの仕組みの定着をさせることができます。さらに、改善活動とISO運用を一貫性のあるものとして再構築することが可能になります。
経営方針に沿った改善活動と、ISO運用が一貫性をもっているかどうか。この視点が、今後の工場経営においてますます重要になってくるのではないでしょうか。