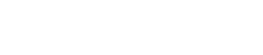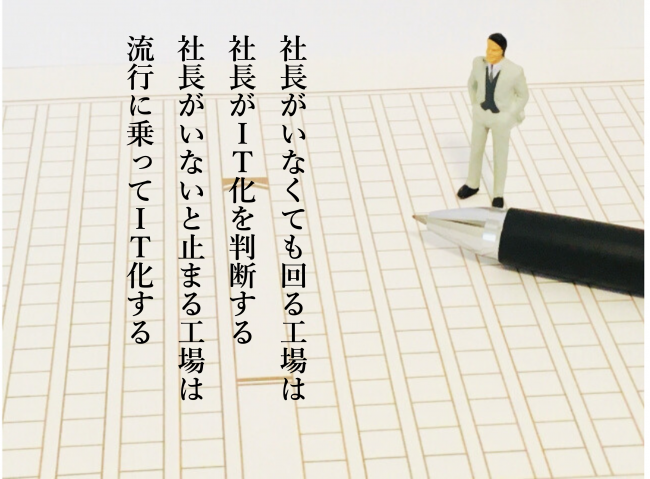
IT化はすでに生活の一部。でも工場は…
IT化という言葉が生まれてからもう何年経つでしょうか。これだけの年月が経てば、ITはできて当たり前、使っていて当たり前、という世の中になっています。スマホは一人1台以上持っていて、買い物はスマホ、電車に乗るときもスマホ、自分の個人情報もスマホに収まりつつあります。それだけ広まりなくてはならないものになっていますし、IT化による恩恵を受けていないという人を探すのも苦労するほどでしょう。
一方で、工場のIT化は遅れていると言われ続けています。
未だに記録を紙に書いたり、紙の資料を管理したり、データ化していても手間をかけて入力していたり、せっかく入力されたデータを活かせていなかったり。
どこまでIT化すれば十分ということはなく、逆にすべてをIT化できればそれでよいかといわれればそうでもなく、どこから手を付けてどのレベルまでお金をかけてIT化するか、この判断がなかなかできず、結果的にIT化にも着手できないという工場が多くあるように思います。
言い換えれば、この判断ができるような人材が工場内にいればIT化は進む可能性は出てきます。
【教育の限界】IT人材育成は万能ではない
IT人材確保のために、社員にIT教育をすることは広く言われていますが、この効果があったという話は実はあまり聞きません。IT人材の教育でよく行われるのは、企業の経営層と現場をつなげる役割を担う中核人材を育てるプログラムの中に、企業の課題をテーマにして、IT化による業務改善をワークショップ形式で学んだり、座学的なものでIT化、AI、データ分析などを学んだり、社長が喉から手が出るほど欲しくなるような、もしかしたら社長以上のポテンシャルを持つ社員を育てる取り組みが行われています。
他には、ITスキルの習得と称して、IT系の資格を取得したり、プログラミング言語を学びアプリ開発を学んだりするプログラムも多く存在します。
ITベンダーにシステム開発、導入を依頼すれば、プログラマー単価1日〇万円、プロジェクト管理費〇〇万円・・・という高額な見積もりを見れば、自社の社員が身に着けて自社で開発、導入できれば相当なコストダウンになります。
ここで社内の現状把握をしてみましょう。
ちょっと考えてみればわかることですが、自社工場内に、社長以上に業務全体を理解し、ITの活用まで判断できるような社員が在籍しているでしょうか?
【現実】IT人材は簡単には育たない
プログラマーが高単価なのはそれなりの理由があります。簡単に言えば、人がそう簡単にできないようなことを生業としているからです。数か月で○○言語を身に着けてIT人材として活躍する・・・とそう簡単にいくようなものではありません。仮に、自社に在籍する社員がそれらをすべてやったとき(どれだけの期間を要するのかわかりませんが)、運用が始まった途端に考えなければならないことが発生します。
それは自作したシステムの品質とそれに合わせて行われる業務の品質です。
この両者を両立することはそう簡単ではありません。
そういう教育を受けてそういう業務につくのだからと、人事評価の仕組みを変えてみても、いくら給与を積み増しても、できないものはできません。
そして次々と発生するシステムのトラブル対応、システムに合わせて必要になってしまった本来不要な業務の追加、それらの対応に追われればコストは増大し、最悪の場合顧客や取引先にも迷惑をかけ信頼を失いかねません。
【社長の役割】IT化の成功は社長の判断力にかかっている
ここまでの話でIT化は全て専門の外部に任せるべきと言っているのではありません。外部に任せる部分、自社でやるべき部分、さらに社長がやらなければならない部分があるということです。
社長がやらなければならない部分で重要なことは、社内の現状把握です。
この量と精度によりIT化の成功は9割決まります。社員のレベル、業務の現状、評価の仕組み、考えなければならないことはたくさんあります。
現状把握をし、何をIT化で解決し、解決することでどんな工場になるのか、これを決めるのは社長しかいません。
IT化ができないのは「IT人材がいないから」という前に、
社長ができることは何かを考え、
思いつきやベンダーの勧め、世の中の流れに惑わされず論理的な思考を持ち、
業務の一部についてシステムを入れて終わりではなく思考範囲を広げて全体最適を考え、
いい話ばかりではなく最悪の事態も考慮しつつ経営判断をすることがとても重要です。
それができるのは、現場を誰よりも理解している社長だけです。
今こそ、社長自身がIT化の旗を振る時ではないでしょうか。