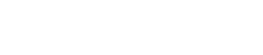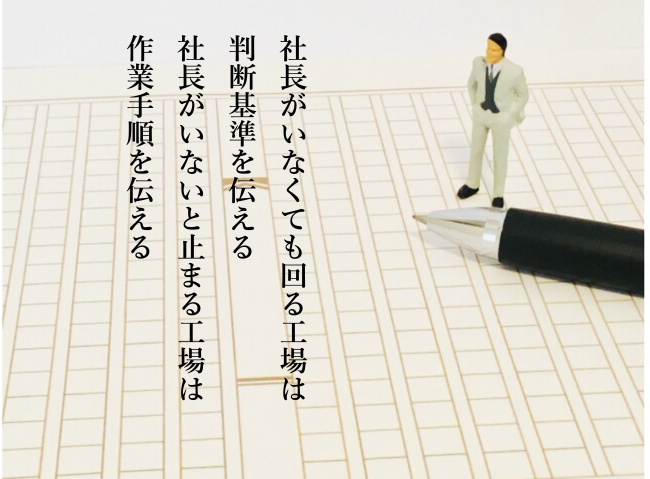
「普通に考えて、そんな作業やらないでしょ!!!」
と顔を真っ赤にして話す社長。
一作業員として入社し、管理職を経て、工場経営を始めて20年になる叩き上げのベテラン社長で、これまで多くの生産ラインを立ち上げては生産性向上のために改善を行い、技術力を高めてきました。
しかしここ数年は、社員の高年齢化が進んだことにより社員の入れ替わりが多くなっており、はじめて〇〇する、という社員が常にいる状態になっていました。
マニュアルに書ききれない「暗黙の了解」
ベテラン社員であれば初めての生産ラインでも、他のラインの経験値から推測し、作業指導がなくてもある程度のことは対応できるものです。だからといってマニュアルが不要というわけではなく、これまでも地道に作成してきました。
しかし、経験の浅い社員が増えるにつれ、従来のマニュアルでは対応できない場面が出てきはじめました。
「マニュアル通りにやったつもり」でも不良品が出る。その作業ミスが発生しないようにと具体的にマニュアルに書かれているかといえばそこまでは書いてない・・・。
だからといって、そんな細かいことまで書き始めれば、いくらマニュアルを作っても間に合いません。
多くのマニュアル作成ツールが出ていて、IT化によりだれでも簡単にきれいに作ることができたり、できたマニュアルをすぐに検索出来て見やすくしたりすることはできますが、そもそも、マニュアルを作る目的は、「誰でも短期間で作業を習得し、ミスがなく作業できるようになること」です。
マニュアル作成をIT化したからと言って、経験値のない社員がミスしないと言い切ることはできません。
作業マニュアルの種類と目的の違い
最近流行りの、スキマ時間にちょっとだけ働くという働き方があり、それが容易にできるようスマホアプリから簡単にそのバイトに応募できるという仕組みがあります。
人手不足を補いたい企業側と、フルタイムでは働けないけど仕事はしたいという人をつなぐための仕組みとして、両者にとても好評のようです。
そのような働き方、雇い方であれば、今日来たその日に頼んだ作業をやってもらわなければいけません。作業指導といって社員が1から10まで指導していたのでは、なにもしてもらえないまま、さらに教えるための時間を割いただけで終わってしまい、とても人手不足解消にはなりません。
したがって、そのようなときに作業マニュアルはとても有効な手段です。
一方で、今回の話はそのような状況を説明しているのではなく、長く定着、活躍してもらいたい社員に対して行う作業指導です。
単なる作業手順ではなく、作業マニュアルにも書ききれないような、言語化が難しい「暗黙の了解」の部分まで理解してほしいと思っての作業指導ですから、従来の作業マニュアルでは不足があるのです。
指示待ち社員を生まないために
作業ミスを発生させないように「作業マニュアル通りに作業する」ということを徹底して身に着けた社員はどうなるでしょうか。
そう、ご想像の通りです。
書いてあることしかできない社員が育ちます。もう少し言えば、書いてないことはしない社員です。
これが上司からの指示でも同じことが言えます。
指示したことしかしない、指示されていないことはしない。
しかしこれは一定程度は仕方のないことでしょう。部下が指示されていないことをやるということは、その場で何らかの判断をしなければいけません。場合によっては、危険、リスクが伴うことになります。気付かないままルール違反をしてしまっているかもしれません。
そして、部下なりに考えてやった結果、冒頭の社長のように真っ赤な顔をして怒られれば、もう指示していないことはしません。こうした方が良いと思ったことが社長と一致していたとしても、「指示されていないからやめておこう・・・」となる悪循環です。
したがって、そんな危険を冒してまで、部下は指示されていないことはしようとしません。
「普通に考えて、そんなことやらないでしょ!!!」というその「普通」とは、社長の中にある社長にしかない判断基準です。思った通りに動いてほしいのであれば、この基準を伝えておかなければいけません。
マニュアル作成は資料を通じた部下への指示です。
作業手順が書いてあるだけのマニュアルも、大前提として気を付けることがあったり、会社の中で常識となっているルールがあったり、判断基準の元となるものがあるはずです。
それを示すことなく作られた作業マニュアルは、1~10まで何も考えずロボットのように、ただただ順番にやりなさい、と言っているようなものです。
指示を受けた部下がミスなく作業できるようなマニュアルにするには、目に見える細かい枝葉を書き切ることが作り込みではありません。目に見えない根っこの部分を深堀りすること、つまり、暗黙の了解や判断基準を明確にすることが重要です。
それと完成形さえわかれば、手書きのメモで十分です。
あとは社員が考えてくれます。