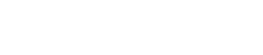工場経営者の皆様、日々の生産活動、本当にお疲れ様です。
私自身も工場経営に身を置いておりますが、並行して、IT化と自主的な社員により工場が社長の手から離れて自走する「工場自動化経営」の仕組みをお伝えするために、工場経営者対象に経営コンサルタントを行っております。
現在みなさまの1日はどのようなスケジュールになっているでしょうか?
新規事業に取り組みたいのに現場を離れられず、銀行向けの説明準備をしたいのに一夜漬け、社員からの問い合わせに振り回され1日が終わってしまう、など今日は何をやっていたのだろうかと思うようなことはないでしょうか?
そのような社長の苦悩は痛いほど理解できます。
私も以前は日勤も夜勤も生産ラインに入って指示をして回ったり、社員間のトラブル対応に追われる毎日。家には寝に帰るだけ。時には機械の横で寝たことも。
しかし、どこかで「次の一手」を打たなければ、程度の善し悪しが変わる程度で根本的にはそのまま、何も変わりません。
この状態が「製造現場のあるべき姿」でしょうか?そして「経営者のあるべき姿」でしょうか?
私たちが目指すべき製造現場の理想の姿とは一体どのようなものなのでしょう? それは、社長は社長の役割を果たし、社員は社員の役割を果たすことです。
社長は現場で指示を出している場合ではありません。社員には給与を払っていますのでそれだけの仕事をしてもらわなくてはいけません。
しかし、もちろん理想と現実は異なります。長年の習慣、人材育成の課題、進まない組織変革、IT化の問題、設備の老朽化など、多くの壁が存在することも事実です。
本日は、私の経営経験と工場経営コンサルタントとしての知見を基に、理想の製造現場と、そこに至るまでの現実的な道のりについて少し深く掘り下げてみたいと思います。
みなさまの工場が、持続可能な未来志向の工場へと進化するための一助となれば幸いです。
⇒「工場経営自動化コンサルティング」についてのお問い合わせはこちら
※関連記事:現場改善コンサルとは?経営者が知っておくべき改善の進め方と実践例
製造現場のあるべき姿とは?
20年以上にわたり製造業界で働いてきましたが、最初は現場の作業員としてスタートし、その後2代目経営者として後を継ぎ、現在は工場経営を行いながら、工場自動化経営を指導するコンサルタントとして活動しています。
これまでに多くの工場での業務のIT化と自主的社員を増やす活動により、工場自動化経営の導入を実現してきました。
例えば、ある工場では古い体質の組織体制の変革とそれに合わせたIT化によるデータ活用を進めることで、納期遅れや品質トラブルの改善にも成功し、同じ売上額を7割の社員で上げることができるようになりました。
さらに、社員の自主性を高めるための制度や教育体制の構築を行い、社長が生産現場から離れても利益を上げることができる、手離れの良い工場を実現してきました。
しかも、わざわざ外部の研修に参加したり、小集団活動を行ってのスキルアップやモチベーションアップもしていません。
このように、製造現場のあるべき姿とは、社長が率先して現場に入り社員に指示をしてリーダーシップを振るうということではなく、社長が現場にいなくても、社員が自主的に業務を進め、生産に集中できる環境を準備することが必要です。
そのためにはIT化はとても重要な方法です。 それと同時にそこで働く社員が働きやすい会社、生産現場でなければどんなにIT化を進めても、決して効率的で高品質な生産を行うことはできません。
実際に、社員がITを使いこなし、自主的に働くことができる環境を構築することができれば、わざわざ社長が現場に入って口も手も出す必要はなく、ある工場の経営者は、月に1回の管理者3名を集めた会議しか出社せず、それ以外は新規取引先開拓や新規事業の開発に時間を費やしておられます。
この成功事例は特定の企業に限ったことではありません。
2024年版ものづくり白書によると、デジタル技術を活用している中小企業は、2019年から2023年にかけて営業利益が増加した割合が高く、賃上げなど従業員の処遇改善も進んでいることがわかります。
また、デジタル技術の活用が進んだ企業では、多くの企業がコスト削減や品質の向上を実感し、4割程度の企業は、人手不足解消や労働時間の短縮・休日の増加など人事面での効果も実感しているようです。
※参考:2024年版 ものづくり白書
多くの企業がこのような成果を出しているため、IT化の重要性は当然理解できるでしょう。
しかし、IT化を行うだけで「製造現場のあるべき姿」になっていると言えるでしょうか?
また、IT化がうまくいっていない企業も少なくありません。あるべき姿を目指す方法がIT化ではない、あるいはIT化以前に問題があると考えられるでしょう。
※関連記事:工場のIT化のためにITの知識よりも必要なこと
製造現場の理想と現実
この章からは、理想を持ちながらも悩み苦しんでいる現実について比較し、「ギャップ」を問題点として捉えて考えてみたいと思います。
※関連記事:製造業の課題を乗り越える解決策!現役経営者が提言する中小企業が取るべき実践的アプローチ
社員の採用と育成
世の中は少子化の悪影響が急激に押し寄せており、大企業でもなかなか新卒社員の採用に苦労しておられるようですが、だれも名前も聞いたことのないような中小製造業であれば、その苦労や負担はさらに大きなものになります。
需要と供給のバランスが大きく崩れている状況ですので、新卒社員の初任給インフレが起こっています。
初任給で中堅クラスの給与を上回っているのではないでしょうか。
経営陣はこのようなアンバランスな状況をどのように制御するのか、非常に興味深く見ています。
そして、やっと、ようやく、何とか採用できたとして、ここからが本当のスタートラインです。
どんなに高学歴で、いくら優秀と思われる新入社員でも、新しく採用された会社で実際にどのような仕事をするのか、それは会社側が提供しなければいけません。
そしてその仕事で成果が出せるよう、新入社員が能力的にも人間的にも成長できるよう育成の場を設ける必要があります。
理想は、 企業側が望む社員像、スキルや知識を持った社員に入社してもらいたい。そしてその能力を活かして会社に貢献してほしい。
しかし現実は、 応募があっただけで奇跡。
能力の有無に関わらずとりあえず入社してもらうこと優先。
入社してもらえれば社員教育で何とかする、と思っていても、実際のところ教育の仕組みがなく、いっしょの職場になった先輩社員任せでその人の負担増。
見てくれればまだよいが、自分の仕事が優先だと新入社員が放置され育てられず、新入社員側からこの会社はもう結構と退職して行ってしまう・・・。
※関連記事:中小工場経営の若者採用で考えなければならないこと
社員の働き方
私の肌感覚ですが、未だ大半の人たちは「昭和の働き方」が身に染み付いて離れないという状況にあるように思います。
現在の40〜50代世代がまだまだ現役バリバリです。
働き始めたときは就職氷河期。何百社と書類を出し何十社と面接をし、ようやく手に入れた就職先。そこでは夜遅くまでのサービス残業や辞めても次を雇えばいいという経営側の強気の姿勢。
そんな人たちがようやく上の立場になった今、自らが経験してきたことを下に教えるという流れは普通の動きです。
したがって20代後半から30代の社員は、そういう人たちからの教えに色濃く影響されるわけです。
ブラックな働き方は良くない、したくないとは思っていても、まだまだそうでなければ業務が進まない、組織で働くことができないという空気感の方が、少し前までは強くありました。
しかしここ近年、急激に変化しています。
例えば、なかなか取ることも憚られた有給休暇や育児休暇。
当時は社歴の長い人や管理職から優先的に希望日に取得できるような暗黙のルールがあったものです。
しかし今では、上司や先輩に気を遣って自分のことは後回しにしてきた方々が、今度は若い人たちに気を遣って有給休暇を取得させたり、その開いた穴を自分で埋めたり・・・。
若い人たちには、その暗黙のルールは無関係なのでしょう。
個人の権利だからと自ら率先して取得しています。
残業規制や有給休暇、育児休暇など社員を守るための法改正がここ数年急激に進んでいることも後押ししているのでしょう。
社員の働き方は大きく変わってきています。
理想は、 全社員が不満なく有給休暇を取ることができ、残業もなく、急な呼び出しもない、仕事のせいでプライベートが侵されることのない働き方ができる会社が良い。
少なくとも、ブラックでなければ良い。
しかし現実は、 そうはいってもそれでは仕事が回らない。
また、最近は休暇の取得も給与の底上げも若い人優先。
今まで苦労してきた社歴の長い社員にしわ寄せが来て、多くの仕事に対応できる社員に負担が偏っている。
仕事を覚えない方が仕事を頼まれることもなく、有給休暇を取っても業務への悪影響も少ないためむしろ自由な働き方ができてしまっている。
人材育成をして仕事を覚えない方がいいと思っているのでは?と疑ってみてしまう。
※関連記事:「社員が育たない」と思うときに考えるべきこと
組織文化
ここまでは工場に限らない、会社で良くある一般的な話をしてきましたが、次からは工場での話に移していきましょう。
いろいろな企業が「組織文化」の重要性や、特に問題が発覚したような企業では、「組織改革」が必要と言われ、工場かそうでないかに関わらず、一般的に企業の重要な取り組み事項だということは紛れもない事実でしょう。
良い組織文化を構築できれば、社内のコミュニケーションが良いものになり、生産性に影響を与え、最終的に利益を出し続ける会社、成長し続ける会社になる、というのが大半の方が思い描く流れでしょう。
これを「工場」という世界で考えてみましょう。 一般的によく言われる「工場」のイメージは、暗い、汚い、危険、重労働・・・などのようなあまり良くないイメージや、清潔、細かい、正確・・・など相反するイメージを持たれている面もあります。
何を作っているところをイメージしているのかで、その答えは変わってくるものと思いますが、 理想は、 暗い、汚い、危険、重労働・・・であることを問題と捉え解決しなければならない経営課題として取り組み、明るく、清潔で、安全な軽作業になれば、若い社員にも選ばれる工場になり、ベテラン職人ばかりの工場が一気に明るく、雰囲気も変わるのではないか・・・。
しかし現実は、 薄暗い工場を明るくするために、あんなに大きな工場に十分なLED電球をつけたらいくらかかるのか?
粉塵や鉄粉などが舞う現場であればいくら掃除しても追いつかない。
危険で重労働な作業を無くそうとすれば膨大な設備投資が必要になったり、設備投資しても極端に時間あたりの生産量が落ち採算が合わなくなってしまう・・・。
今の環境でものづくりするのが精いっぱいで、組織改革どころではない。
※関連記事:組織を変革するのはだれ?
工場の生産管理
工場では、製品が完成するまでに多くの工程があり、その工程内をスムーズに人と物が流れるように管理をする業務があります。
一般的に間接業務と言われる業務です。 受注、スケジュール作成、材料確保、生産指示、納期管理、在庫確認、設備能力の管理、生産実績の把握などなど、やることはたくさんあります。
在庫管理システムや生産管理システム、ERPなどの基幹システムなどを構築して生産性の向上を目指している工場は多くあるでしょう。
工場の規模の大小に関わらず、また生産性向上を目的とせずとも業務のIT化は必須の取り組みとなっています。
理想は、 そんな世の中の流れに乗り、あるいは乗り遅れないように、管理システムの導入を行い、管理業務をできるだけITに任せ、できるだけ少ない人数で管理業務を回したい。
そして空いた時間にもっと人にしかできない業務を行い、利益が出せる工場にしたい。
さらに現場では設備のデータを取得できるデバイスをつけリアルタイムで状況把握できる環境を整え、素早く的確な指示が出せるようにしたい。
しかし現実は、 管理業務の効率化にはIT化は必要だと思って取り組んだのに、結果的にはシステムを操作できる人が限られていて、その業務が属人化してしまったり、その人は生産業務でも優秀な社員なので生産体制が崩れてしまう。
さらにその社員だけに負担がかかり現場の生産効率まで下がり、システムも予定通りに稼働させることができない。
システム導入したことにより、今までその業務を行っていたシステムを触れない社員は、これからいったい何をすればいいのか・・・。
経営者の役割
一般的に経営者の役割といえば、どんなものがあるでしょうか?
毎日現場に出て社員と一緒に作業している社長もいれば、平日でもゴルフに行っていたり、何をしているのか分からない社長もいます。
見える部分だけ話していても意味はありません。
経営者にしかできない重要なことさえやっていれば、それを社員が納得していれば会社は回ります。
では、工場の経営を行う経営者の役割とは何でしょうか?
理想は、 生産現場は工場長以下の社員に任せ、社長は取引先の開拓や新商品開発、新規事業の開発に着手したい。
またそれを実行するためには時間と資金が必要なので、経営計画の作成をし金融機関にプレゼンしたい、取引先にプレゼンしたい、ゴルフをしてもっと濃い付き合いをしたい・・・。
しかし現実は、 あれこれ手を打ってきた現場なのに、 新入社員はなかなか育たないので、社長が自ら現場に入って手をかけて教育しなければいけない。
組織改革は必要と考えているが、社員は社長の話を聞くだけ、指示を待つだけ。社員のモチベーション維持方法が社長の喝入れが頼り。
社員に有給休暇を取らせなければならない、残業をさせられないので、社長が自ら生産現場に入って作業する。
そもそも、社員が有給休暇を取るという空気にもならない。
生産管理的な業務ができる社員がいないため、自ら現場に入って指示を出さなければいけない 。
また、生産管理システムを導入したのに、データ活用することができず、現場現物現実の三現主義に基づいて走り回っている。
結局社員は感覚基準の指示を出し、社長がそれを調整する指示を出さなければならない。
※関連記事:工場経営者が持つべき価値観
経営者が製造現場のあるべき姿を目指すには?
製造現場の理想を語るとき、どうしても「現場改善」や「社員育成」ばかりに目が行きがちです。
しかしそれらの対策は全て、社長がベストな工場の仕組みを構築している場合を前提としてはじめて効果を発揮するものであって、現場改善や社員育成そのものは問題解決につながるひとつの手法でしかありません。
実際にやってはいるのにその効果がよくわからないといったことはよくあることです。
したがって、組織改革、現場改善などを行って現場を変えるためには、まずは、経営者自身の思考と行動の変化が問われます。
ここでは、経営者自らが経営スタイルを振り返るために「5つのチェックポイント」をご紹介します。
これらは、私自身の経験や、コンサルティングを通じて多くの工場経営者と接する中で見えてきた、共通する課題でもあります。
経営者がチェックすべき5つのこと
.png)
経営者は「ものづくりのプロ」である必要はない
製造業の経営者というと、現場の技術や製品に精通していなければならないと思われがちですが、実際には「経営のプロ」であることの方が重要です。
現場の細かい技術は、信頼できる社員や専門家に任せるべきであり、経営者は「全体最適」を考える立場に立つ必要があります。
したがって、プレーヤーではなく、マネージャーであることが重要です。
現場で社員と一緒に汗を流すことは、時に信頼を得る手段にもなりますが、信頼獲得手段をそれに依存することは実は経営者としての仕事を放棄していることと同じです。
経営者の本来の役割は、現場を動かすことではなく、現場が自走できる仕組みを整えること。
プレーヤーではなくマネージャーとしての視点を持って現場を見ているか、一度確認してみましょう。 現場の社員に、社長は社員よりもたくさん作る人、上手に作る人、と思われていたら手遅れ寸前です。
社員の能力だけでなく、自分自身の能力も把握する
社員の評価や育成に力を入れる一方で、経営者自身の強み・弱みを客観的に把握している方は意外と少ないかもしれません。
評価をする側と思っていたら大間違いで、全社員が経営者の仕事ぶりを評価しています。
社員から評価を下されることはないかもしれませんが、社員ががんばって成果を出してくれる、社員がやる気をなくして退職をする、などの行動は紛れもなく社長に対する社員からの評価です。
経営者は社内で「経営」という仕事を任された立場です。
自分が得意なこと、苦手なことを明確にし、苦手な部分は何かで補い、経営という役割を全うし、社員には生産業務を全うしてもらうことが、組織全体の成長につながります。
社員に対する発信力は「言葉」や「行動」だけではない
経営者の考えや方針は、経営理念やビジョン、方針など明文化した言葉で発信することはとても重要です。
しかし、それだけでは不十分なことは誰でもわかることでしょう。
具体的に何をすればいいのか、どのように動けばいいのか、自ら動いて行動で見せることも必要でしょう。
しかしこの場合も、社員のだれもが社長のやった通りに作業ができるとは限りません。
この工場では、どのようなことを考え、どのように業務を進めればよいのか、言葉や行動だけでなく、「制度」「仕組み」「評価基準」「社内ルール」などを通じて伝わります。
社長がどんなに良い理想を語っても、それを行ってもよいルールがなければ実行もできませんし、評価される仕組みがなければやるだけ損になりかねません。
そのような環境下では社員に何を言っても伝わらないのです。
工場である前に「会社」である
製造業の経営者は、どうしても「工場=会社」と捉えがちです。
さらに、「仕事=製造」と捉えられる面もあり、それが組織づくりや業務効率化に悪影響を及ぼしています。
会社は、製造部門だけでなく、営業、経理、人事、総務、情シスなど非製造部門も加わり連携して成り立っています。
小規模事業者と言われる20人未満の会社でも、仕事量は少なかったとしても、必ず誰かがその業務を行っています。
したがって、生産現場の工程改善や作業者のスキルアップに注力して生産能力を上げようとしても、会社全体としては成長が見られないということが起こり得ます。
工場は製品をつくる場所ですが、会社は「人と組織が価値を生み出す場」です。
製造現場だけでなく、会社全体を俯瞰し経営する視点が求められます。
全体最適を目指した経営を行っているか見直すことが、持続可能な経営への第一歩です。
社員も社長も、一人の「人間」である
社員を「労働力」としてだけで見ていないでしょうか。
「人それぞれの人生の一部の時間を、たまたまこの会社で共にしている」として見ることができるかどうかはとても重要です。
人生の3分の1は睡眠と言われていますが、残りの3分の1かそれ以上は、この会社で過ごすわけです。
その時間の過ごし方によっては、社員の人生も左右してしまうと考えなければいけません。
社員も社長も含め、会社という場が、それぞれの個人の人生を豊かにする場、人間的にも成長できる場であることが、信頼関係の構築につながり、人間関係の質が組織の質を決めることにもつながります。
これはどんなにIT化が進んでも、どんなに優秀なAIがいたとしても、経営の本質として変わらない部分です。
まとめ
製造現場のあるべき姿について、理想と現実を対比しながら見てきましたが、製造現場のあるべき姿を目指すには、経営者自身が理想の経営者像に近づいていくことも必要になってきます。
理想の経営者像とはどういうものでしょうか?
ここで言い切れるのは、会社で行われている業務についてすべてに精通していてすべてを完璧にこなすことができる人、ではないということです。
社員が自らすすんで業務を進めることができるよう、働く環境を整えることは重要な社長の仕事です。
それを実現するにはどのような経営者になるか。その答えは社長の数だけ存在します。
そして、最後に5つのチェック項目を挙げましたが、これらは経営者自身の「立ち位置」を見直すために、定期的に確認してみることが重要です。
すべてを一度に変える必要はありません。まずは「自分が最も必要だ」と感じた部分から取り組んでみてください。
それだけでも組織は変わっていくはずです。
しかし経営者には「預金口座」というタイムリミットがあります。 どんなに良いことに取り組んでいても、預金口座が0になったら終了です。1秒でも早く取り組む必要があります。
さくらブルーでは、「工場経営自動化コンサルティング」で現場を社員に任せ、社長が次のビジネス展開に専念できる仕組み構築のノウハウを提供しています。
自社の経営にお悩みの工場経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
⇒セミナーやコンサルに関するお問い合わせはこちら