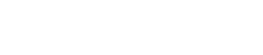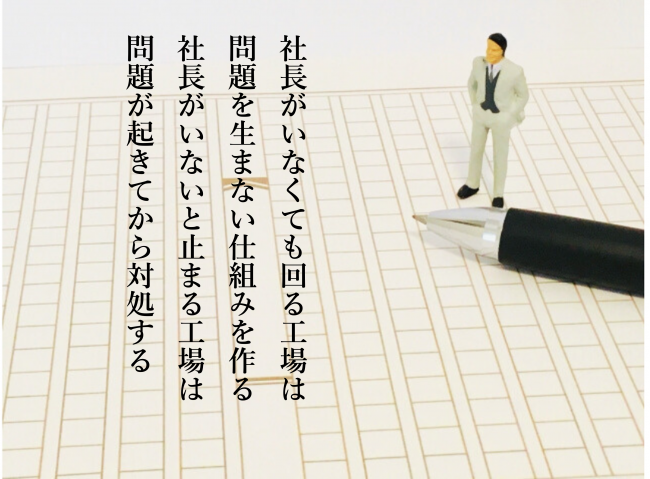
昨今、○○ハラスメントという言葉が定着し、○○の部分が非常に多くの種類が登場するようになってきました。
直近では「カスハラ」でしょうか。カスタマーハラスメントです。
特にサービス業などお客さんとの直接的なやり取りの多い業種で起こりやすいようで、様々な企業や行政まで対応マニュアルが作成され、簡単に言えば、そういうお客さんはこちらからお断り、と言えるような対策を講じておられます。
ようやく、お客様は神様という状態から対等な立場でのやり取り、取引でなければならないということが定着し始めたのではないでしょうか。
お互いにできないことがあり、できることを提供しあって世の中成り立っているのですから、お客様は神様だからお客様のいうことには逆らってはいけないという風潮がなぜできてしまったのか、私には到底理解できません。
ある行政職員さんの話です。
昔はとても横柄な態度の職員が多く、雰囲気も悪く、そのことについて市民からの苦情はあるにはあったが、それに対して敏感になる人もなかったとのこと。
職員の態度の悪さを改善しようとしない行政側にも問題はありますが、苦情を言っている市民側にも一定程度の問題が。
それは、苦情を言うだけムダ、行政はそんなもん、とその状態を改善することを止めていたとも考えられます。
確かに私もいろいろな手続きで資料を持って行ったものですが、今思えば理不尽なやり直しにも黙って言われる通りにやっていたなあと思い出します。
また、飲食やアパレルなど一般的なサービス業では、ココがダメなら隣の店で、というように簡単にお客さんは逃げていきます。しかし行政サービスの業務は、そこで対応してもらわなければ他にやってくれるところはありません。それをいいことに、前述のような態度の悪い殿様商売的なものがずっと残ってしまっていたのでしょう。
この状況が、あなたが経営する工場でも起こっていないでしょうか?ということです。
現在は、人材不足で悩んでいる会社はホントに多く聞きます。
しかし、一昔前では、「あいつが辞めても次を雇えばいい」と平気で言う社長がホントに多くいたものです。就職氷河期の年代の方々は特にそれを実感していることと思います。
何十倍の倍率でなんとか大学に入学し、何百倍の倍率の就職活動を乗り越えなんとか入社した会社で、まだ言葉にもなっていなかった様々なハラスメントを受けながらも、ここを離れたら次のはないという、どちらに転んでも地獄のような立場にあった人も多くいました。
それが世の中の物事の考え方の変化と、少子化により構造的に会社の数より仕事を探す人の方が少なくなってしまったことにより、立場が一気に逆転し「こんな会社、いつ辞めてもいいんですよ」というナイフを突きつけられながら経営をしているという社長がとても多くなりました。
行政も横柄な態度のままでは行政サービスが成り立たなくなると危機感を感じ、様々な対策を行ってこられたのではないでしょうか。至る所で職員さんの対応がとても変わったのを実感します。
民間の会社を経営する社長も、一昔前の考え方ではとても問題があるのはもちろんですが、行政のそれよりとても危機感を感じて対応しなければいけません。地域の住民が減っていくこと、他の地域から人が来なくなることは問題ですが、小規模工場では社員が1人減るだけでもインパクトは大きく、事業の存続に直接的に影響を与えます。
更に行政が提供しているものと工場が提供しているものを比較すると、行政サービスは行政でしか行われていないという特殊なサービスで、社長が経営する工場は、何百社、何千社と、全国各地に自社と同じことをする工場が存在しているということです。
社員が働く場所を選ぶには、別にその工場でなくてもよいのです。
それを引き留めるために、あるいは新たに来てもらうために、初任給を上げてみたり福利厚生を充実させてみたりする企業は多くありますが、果たしてあなたの会社で働きたい人はそれを求めて働きに来ているのでしょうか?今残ってくれている社員はあなたの会社の何がよくて残ってくれているのでしょうか?
社員のみなさんにそれを聞いたことがありますか?
はじめからホントのことをすべて話してくれることはないと割り切った方がいいですが、何も聞かずに推測で判断し、人が足りないからと募集をかけ、それでも人が来ないからお金をかけ採用し、利益が出ないからといって昇給もない、という悪循環を生んでしまっているかもしれません。
しかし、社員の話を聞き、社内をよくよく分析すると、採用する必要がないかもしれません。
そのような芽を探し、悪循環を断ち切らなければいけません。
その悪循環の中で新たな取引先を探し売り上げを上げようとすることは、より悪循環を招くことになります。
悪循環を断ち切れば、社員から逆ハラスメントを受けている社長も、そんな社員に怯えることなくさっさと辞めてもらった方が生産効率は上がります。
ハラスメントの対処法はハラスメントの事例の分だけたくさんありますし、起こってしまった事案に対処することは優先的にしなければならないことではありますが、ハラスメントを生み出さない工場の仕組みを作ることの方が重要です。生産現場で品質保証できる環境を作ることと同レベルかそれ以上重要なことです。
社員が自主的な業務に取り組むことができる環境作りは、当社が提唱する工場自動化経営では、必須の取り組みです。モノを作らなければ売上になりませんが、仕事ができる環境がなければモノも作れません。