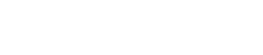はじめての方へ
For First-Time
Visiter
「社員×IT」で、手のかかる工場を
社長がいなくても利益を生み出す
「自動稼ぎ装置」にする仕組みを提供します
自分が指示を出さないと現場が回らない。 社員が指示待ちで、自主的に動いてくれない。
トラブルがあればすぐに社長に報告、対応するのはいつも社長。
そんな状態では、社長は現場に手足脳みそを奪われ、 本来やるべき経営戦略や新規事業開発に時間を使うことができません。
社長が現場に張り付いている限り、企業の成長は止まってしまいます。
もし、社長が月1回の会議に出るだけで、 工場が自動的に利益を生み出し続けるとしたら、どうでしょうか?
それを実現するのが「工場自動化経営」です。
Our Concept
工場自動化経営とは
工場自動化経営とは、単なる生産の機械化や設備の自動化ではありません
当社ウェブサイトにお越しいただきありがとうございます。株式会社さくらブルーコンサルティング代表の蓑原です。
当社は、工場自動化経営コンサルティングを行っています。工場自動化経営とは、単なる生産の機械化や設備の自動化ではありません。
「仕組みと組織の自動化」により、 手のかかっていた工場を、社長が現場にいなくても利益を生み出す 「自動稼ぎ装置」へと進化させる経営手法です。
具体的には、以下の3つの要素を組み合わせて実現します。
1.作業の機械化による自動化
2.業務のIT化による自動化
3.社員が組織の一員として自主的に業務を遂行する自動化
これらを実現することで、現場は社員だけで回る工場になり、社長は現場を社員に任せて、新規事業の立ち上げ、工場の増設、新商品の開発、新規顧客の開拓など、現場対応に縛られることなく、次のビジネス展開に専念することが可能になります。
Why now?
なぜ今、工場自動化経営が必要なのか
現場改善の延長に、次のビジネス展開はありません!
中小製造業を取り巻く環境は、かつてないほど厳しくなっています。

深刻な人材不足
知識・経験・技術を持った人材の退職や、若手人材の確保が困難になっているが、採用してもすぐやめてしまう

賃金上昇圧力
世の中の賃金上昇の流れと、最低賃金の上昇により、人件費負担が年々増加

資材価格の高騰
円安などの影響による原材料費の上昇で利益率が圧迫される

若手社員との価値観のギャップ
従来の指導方法が通用せず、育成に時間がかかる

属人化のリスク
特定の社員に業務が集中し、その人がいないと工場が回らない
これらの課題を、従来の「改善活動」や「工数削減」だけで解決しようとしても、 根本的な解決にはなりません。
必要なのは、経営の仕組みそのものを変革することです。
工場自動化経営により、これらの課題を根本から解決し、持続可能な工場経営を実現することができます。
Core.
工場自動化経営3つの柱
工場自動化経営は、次の3つの柱で構成されています。
柱1.業務の仕組化
社長の指示がなくても、社員が迷わず業務を進められる仕組みを構築します。
柱2.人材の自動育成システム
社員任せのOJTに頼らない、体系的な人材育成の仕組みを構築します。
柱3.自律的な問題解決の文化
報告・相談に頼らず、社員自身が判断・行動できる組織文化を構築します。
これらの取り組みには、生産の実務以外に、組織運営の知識、法的な知識、ITに関する知識、社員の特性の理解、業務の難易度など様々な知識やその時点の状況を考慮する必要があります。
工場経営の自動化の自動化は、高機能なシステム導入を勧めるITベンダーや、生産ラインの工数削減を勧める製造コンサルタントのいう通りに行えばできあがるような簡単なものではありません。自社のことを一番よく知る社長にしかできない重要なことです。
Why It Fails
従来の方法では、なぜうまくいかないのか
多くの工場で行われている「改善活動」では、経営の根本的な課題は解決できません。
生産ラインの工数削減では不十分
小集団活動で工数を削減しても、それは部分最適にすぎません。 1日あたり10分の時間短縮を3ヶ月かけて実現しても、 経営への影響は限定的です。 また、生産技術的な知識が必要なため、 実際に活動しているのは限られた社員だけになってしまい、 特定の社員の負担が増えるだけの結果になりがちです。
高額なシステム導入だけでは解決しない
ITベンダーが勧める高機能なシステムを導入しても、業務の仕組みが整っていなければ、効果は得られません。
むしろ、余計な作業が増えたり、システムに振り回されたりして、「結局、社長が確認しないと不安」という状態に陥りがちです。
高額な投資をしても、減価償却が残り、利益を圧迫します。
5S活動では経営は変わらない
5S活動を10年続けていても、5Sあるいは製造等のコンサルタントがいなければできない状態であれば、 それは真の改善とは言えません。 整理整頓は重要ですが、それが社長が現場から離れられる要素にはなりません。
Transforma
tion.
工場自動化経営で実現できること
工場自動化経営を導入することで、以下のような工場に変わります。

社長が月1回の会議に出るだけで工場が回る
週に1回、あるいは月に1回の会議で現場の状況を把握し、 次のアクションを指示するだけ。それ以外の時間は、 新規事業開発や顧客開拓など、経営活動に専念できます。

社員が自ら判断し、行動する
指示待ちの社員ではなく、自ら考え判断し、行動する社員に代わります。問題が発生しても、社員自身で解決できる体制が整います。

人材育成の負担が大幅に削減される
採用後すぐに戦力化でき、教育担当者の負担も軽減されます。安定した品質の人材を継続的に育成できる仕組みが整います。

属人化が解消され、誰でも同じ成果を出せる
特定の社員に依存せず、誰がやっても同じ品質、同じ成果が出る工場になります。退職や異動の影響を最小限に抑えられます。

安定した利益を継続的に創出する
高額な設備投資やシステム投資なしに、確実に高利益体質の向上に代わります。工場が「自動稼ぎ装置」となり、社長がいなくても利益を生み出し続けます。

次の事業展開に専念できる
社長が現場から解放されることで、経営者として本来やるべきことに専念できます。新規事業の立ち上げ、新規顧客の開拓、新製品の開発、事業拡大など、次の攻めのビジネス展開にチャレンジできるようになります。
Before & After.
社長の1日が変わる
工場自動化経営を実現し、工場が「自動稼ぎ装置」になると、社長の1日のスケジュールは劇的に変わります。

Before:工場自動化経営の導入前
ー 始業前から現場に入り、生産状況を確認し生産の段取り
ー トラブルが発生すれば駆けつけて対応
ー 社員からの質問や報告に対応
ー 夕方まで現場に張り付き、作業指示
ー 経営戦略、新規顧客開拓を考える時間がない
ー 社員が育たない
ー 休日も現場のことが気になる

After:工場が自動稼ぎ装置になると
ー 週1回、または月1回の会議で現場状況を把握
ー データで現場の状況を確認、必要な指示を出すだけ
ー トラブルは社員が解決、重要事項のみ報告
ー 新規事業の企画、立案、営業活動に注力できる
ー 戦略的な経営判断に時間を使える
ー 自分の仕事を夜や休日に回す必要がない
ー 休日は完全にリフレッシュできる
FAQ.
よくある質問
Q1:コンサルティング期間中に、設備投資やシステム導入は必要ですか?
A.いいえ、必要ありません。工場自動化経営は、高性能な設備や高機能なシステムの導入を前提とせず、それだけに頼らない経営の実現を前提としています。そのため、高額な投資も減価償却も残らず、確実に高利益体質の工場になります。
Q2:現場の生産ラインを止める必要がありますか?
A.いいえ、生産ラインを止める必要ありません。生産ラインそのものを改善するのではなく、通常の生産活動をつづけながら、経営の仕組みを構築することが目的です。現場へのしわ寄せはありません。
Q3:コンサルティングで社員に生産から抜けてもらうなど、社員に負担をかけませんか?
A.社員に余計な負担をかけることはありません。当コンサルティングでは、社員に直接指導する、宿題を与えるなどの負担はかけません。経営の仕組みを明確にすること、それを実行することが目的ですので、社長には負担がかかるかもしれませんが、むしろ社員は安心して生産に集中できる環境を構築することができます。
Q4:どのくらいの期間で効果が出ますか?
A.コンサルティングは全8回のプログラムを約1年かけて実施します。この時点で、社長が週1回、月1回の会議で現場が回るようになる企業もあれば、その後数年かけてやっと実現するという企業もあり、会社の状況によって様々です。しかし、プログラム終了時点でやるべきことがまとまった資料が出来上がりますので、これを繰り返すことで精度は上がっていき、社長が不在でも現場が回る仕組みを自社で作り上げていくことができます。
Q5:ITやシステムに詳しくなくても大丈夫ですか?
A.大丈夫です。高度なITスキルは必要ありません。コンサルティングでは、スマートフォン、PCを日常的に使える程度のスキルがあれば十分です。
Q6:自社でも本当にできるのでしょうか?
A.できます。しかし、工場自動化経営とは、コンサルティングを受けるだけで誰でもできるというものではありません。社長が週1回、月1回の会議だけで現場が回るようになるには、それなりに時間と労力は必要です。当コンサルティングでは、体系化されたノウハウを「コンサルティングブック」にまとめており、順番に取り組めば確実に成果が出る仕組みになっています。特別な知識や技術は不要です。社長が本気で取り組む意思があれば実現できます。
Q7:他のコンサルティングとの違いは何ですか?
A.工場自動化経営は、生産技術や工程改善による生産性向上を行うものではなく、組織運営、IT活用、人材育成など様々な視点から工場経営に必要な要素を体系的に扱います。また、コンサルティングは、工場経営を実際に行っている、当社代表が直接行います。工場経営者として自社で実践し、成果を出している経験に基づいたコンサルティングです。机上の理論ではなく、現場で使える実践的なノウハウを提供します。